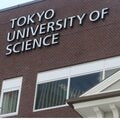実際に大事件に遭遇した経験者も、精神的な厳しさを訴える。
2008年に東京・秋葉原で発生した無差別殺傷事件では、7人が死亡し10人が重軽傷を負った。都内で精密機器部品製造業を経営する鈴木敏文さんは、当時現場に居合わせた。
「誰か、誰か」という声を耳にした。ハンチング帽の男性が腹部をおさえながら片ひざをついている。駆け寄り、横になった男性のシャツをまくりあげると、むき出しの内臓が目に飛び込んできた。「誰か手伝ってください」と応援を求めると、男性2人が応じてくれた。弱っていく男性に声をかけ続け、救急隊員に引き渡したが、男性はその後死亡したという。
「救命にあたっているときは不安になるんです。体の向きはどうすればいいのか、痛みを和らげるにはどうしたらいいのか、水を飲ませてもいいのか――。手当たり次第に知っている病院に電話をかけましたが、『現場の救急隊の指示を待ってくれ』としか返ってこなかった。男性の死を知ったのはその日の夜。助けられなかった者としての責任を、今でも感じています」
鈴木さんによると、秋葉原の事件では、けが人が広い範囲に散らばり現場は混乱。居合わせた1人の男性医師が駆け回っていた。けが人を1カ所に集めていれば、男性医師の力をもっと生かせたのではないかと、鈴木さんは悔やむ。救急隊が治療の優先順位を決める「トリアージ」も、手間取っているように見えたという。
多数の傷病者がいる時は、色つきタグなどで重症度を区別し、治療の優先順位を決める。歩行の可否や意識の有無、呼吸の程度や脈拍などを確認し、どんな傷病を負っているか把握する。症状が悪化するにつれ、タグの色も変わっていく。
今回の川崎市の事件でもトリアージは行われたが、前出の照井氏は改善すべき点があるという。
「救急車で一人一人搬送していること自体、間違いです。スクールバスでもタクシーでも何でも使って、できるだけ早く全員を近くの病院に運ぶべきでした。トリアージで区別している時間がもったいない。病院に行かなければ輸血もできないのですから、医師を現場に派遣しても意味がありません」
一般市民がトリアージをするのは難しいので、まずは救急隊員が到着するまで、止血や心肺蘇生をすることが求められる。
事件や事故の現場に出くわすことは想定したくはないが、可能性は誰にでもある。いざという時何ができるのか、普段から考えておきたい。
(本誌・緒方麦、亀井洋志)
※週刊朝日オンライン限定記事