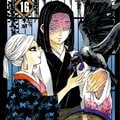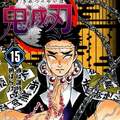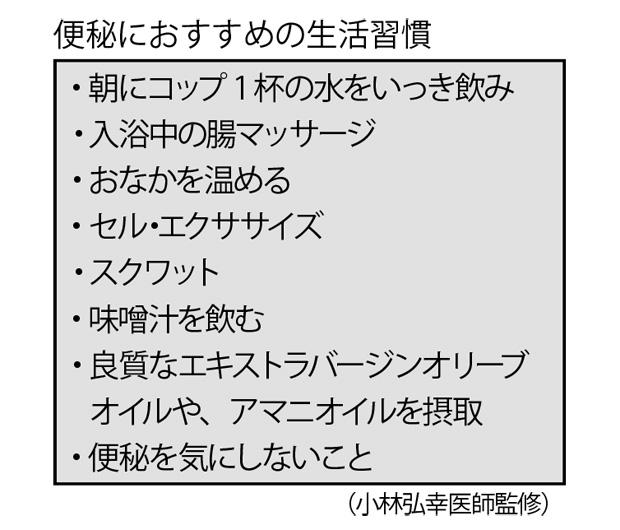
若い女性に多いイメージの便秘だが、病院の便秘外来を訪れる8割以上は中高年だという。出てもすっきりしない。年齢と共に腸内環境が悪化し、筋力が落ちてくる中高年の便秘の問題は深刻だが、安易な下剤の摂取はNGだ。
* * *
安易に下剤に頼るのはよくないと警告するのは、西の便秘のスペシャリスト、大阪医療センター非常勤医師で道仁病院(大阪府)院長の宮崎道彦医師だ。
大阪医療センターは、関西で最初に便秘外来(肛門、排便障害外来)を構えている。
医療機関で処方される下剤や、市販の下剤薬、下剤効果のあるお茶などに含まれる薬剤を宮崎医師は問題視する。
「センノシドとか、センナ、大黄といった成分を含むアントラキノン系薬剤は避けたほうがいい。これらを長く服用すると、通常はピンク色であるはずの大腸の粘膜が、チョコレート色に黒ずむだけでなく、便秘は慢性化します」
■便秘の原因は蛇口か水道管
厚労省のホームページにも、「耐性の増大等のため効果が減弱し、薬剤に頼りがちになることがあるので長期連用を避けること」とある。一般的に、これらの薬剤はドラッグストアでも売られており、手に取りやすいのも問題だ。
「問題は、そういった薬を一般の医師が処方している、ということです」
漢方系の薬剤名を聞くと、「体によさそう」というイメージを持つ人も多いだろう。だが注意しよう。
医師から処方された場合、
「それには、アントラキノン系薬剤が入っていますか」と聞ける勇気を持つことも大事だ。
宮崎医師は患者に対して、便秘の原因がどこにあるのか、排便通路を水道に例え、問題が蛇口(直腸肛門型)にあるのか、水道管(結腸型)なのかを調べるために、大腸内視鏡検査、直腸肛門内圧測定、排便造影検査の三つの検査を行う。
「いわゆる便秘症」に多いのが、水道管の問題。その場合は、腫瘍性疾患やクローン病、潰瘍性大腸炎、感染症などの炎症性腸疾患や過敏性腸症候群が除外できれば、内服で治療する。