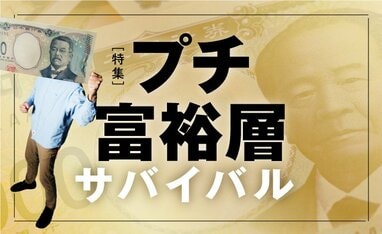ドラァグクイーンとしてデビューし、テレビなどで活躍中のミッツ・マングローブさんの本誌連載「アイドルを性(さが)せ」。今回は、「慶応ブランド」を取り上げる。
* * *
良くも悪くも『慶応ブランド』なんてものは、昭和の時代から幾度となく持て囃され、“こすり”続けられてきた結果、今や完全に形骸化した幻想(ファンタジー)の賜物でしかないと思っていました。野球の早慶戦しかり、政界・財界・医学界における学閥しかり、石原裕次郎に代表される慶応ボーイしかり、確たる伝統や効力はあるにせよ、甚だ時代遅れなイケイケ感満載です。そしてここへ来て、悪目立ちばかりすることが多い慶応……。縦の繋がり横の繋がりともに“最強の切り札”として、この学歴国家で幅を利かせてきた「大学は慶応です」というフレーズが、いよいよギャグになる日は近い?
東大や京大や藝大が日本人にとっての『学歴の極み』であるように、『慶応』もまたある種、日本人の価値観“そのもの”として存在してきました。かく言う私もその価値観の中で育ち慶応を出た人間です。創設者・福沢諭吉による有名な一節は「天は人の上に人をつくらず、人の下に人をつくらず」ですが、その後には「されど学や経験を身につけておかなければ、この世の格差は渡っていけない」と続きます。オイシイところは持っていく洗練されたフットワークと潰しの利く要領の良さ。そんな根拠無き自己暗示を継承し、印象づけることによって、慶応の漠然たる神話性は現在に至ります。もちろん多分野にわたり結果や人材が輩出していることには変わりありませんが、もはや『慶応』は芸やネタの域に入ったと言ってよいでしょう。