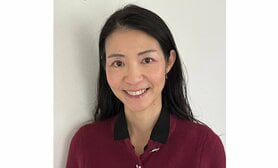京セラ、第二電電(現KDDI)を創業した稲盛和夫氏は、1997年に在家得度を受けた。稲盛氏は仏門に入った理由をこう語る。
――会長は60歳を超えてから、仏門に入られたと伺いましたが?
臨済宗妙心寺派の円福寺で、西片擔雪(たんせつ)さんというご老師の導きで、得度をさせていただきました。
――なぜ得度をされたのでしょうか?
自分は80歳くらいまで生きるだろうと想定し、人生を3期に分けて考えていました。生まれてからの20年が第1期。これは社会に出るための準備期間です。その次の40年は社会のために働く期間です。第3期、最後の20年を、死ぬための準備期間としていました。
その準備の一つが、得度だったのです。
――実際は、65歳で得度されたのですね?
ええ。60歳のときは仕事が忙しすぎて、とても無理な状態でした。65歳になって、これ以上先に延ばすことはできないと考え、京セラとDDI(当時)の会長職を退き、得度の準備を進めていました。ところが、その2週間ほど前に健康診断に行きましたら、精密検査をしましょうと言われたんです。
――何だったのですか?
胃にがんが見つかったのです。ちょうど得度と修行のためにスケジュールを空けていたので、得度する予定だった日に手術をし、胃を3分の2ほど切りました。手術から1カ月後には何とか退院できました。病み上がりで、まだふらふらしていたのですが、早くお釈迦様の教えを学びたいと思い、9月7日に円福寺で得度式を行いました。
――修行中、印象に残ることはありましたか?
ようやく起きられるようになった状態でしたけど、夜中まで行をやっていました。朝ご飯はお粥で梅干しとたくあんがおかず。20代の若い雲水はみな2、3杯も食べるのですが、私は病み上がりで1杯もなかなか食べられませんでした。
――過酷ですね。
ええ。草鞋(わらじ)を履き、網代笠(あじろがさ)をかぶり、墨染めの衣を着て、頭陀袋(ずだぶくろ)を首から下げて、托鉢(たくはつ)に出かけます。一軒一軒檀家を回って、1合2合のお米をいただきますが、10軒も回るとお米を入れた頭陀袋も相当、重たくなるのです。檀家で食事を頂戴したこともありました。その家のおかみさんに「新しいお坊さんが来ると聞いたので、てっきり若い人と思ってラーメンを作ったけど、年寄りならそばがよかったね」と言われたこともありましたよ(笑)。
――何を悟られましたか?
夕方まで托鉢をして、疲れた体を引きずるように歩いていたとき、公園を掃除していた年配の女性が「これでパンでも食べてください」と、100円玉を恵んでくれました。それをいただいたとき、私はとても幸せな気持ちになりました。あまり豊かそうには見えないご婦人が、何の気負いもなく、私にお布施をくださる美しい心に触れ、言いしれぬ感動を覚えました。これが神仏の愛かと実感しました。
――その後、修行は?
05年から、山陰、四国、信州、東北などいろいろな地方を回り、托鉢をしました。托鉢をする街の禅寺の若いお坊さんも一緒に歩いてくれてね。いただいた浄財は、各地の児童福祉施設に喜捨しました。
――稲盛会長が托鉢されれば、多くの人が集まったのではないかと思いますが?
いえ、今時、網代笠をかぶって、70歳代の雲水が、声を出して歩いても、若い人たちは足をとめてくれませんよ。辻説法のときには、私の本の読者たちがそれなりに集まってくれましたが、おのずと限界があります。それよりは、市民フォーラムを開いたほうが多くの方々に聞いてもらえるのではないかと考えるようになりました。
――最初に仏の教えに接するきっかけとなったのは?
故郷の鹿児島では、江戸時代に薩摩藩によって一向宗が弾圧されたとき、「隠れ念仏」として信仰を守ってきました。私が小さい頃は、まだその習わしが残っており、4歳か5歳の頃、父に隠れ念仏へ連れていかれたんです。
――どんな経験でしたか?
お坊さんの後ろで正座をしてお経を聞いていました。終わってから線香をあげ、お坊さんに、「これからは、仏様を『なんまん、なんまん、ありがとう』と言って拝みなさい」と言われました。仏様に感謝して毎日生きなさいということだったのですが、この言葉は、人間が生きていくには、感謝の気持ちが大事であると認識させられるきっかけにもなりました。今は自然と、すべてに心からの感謝の念がわいてきます。
――今にして思う、人生の意義とは?
仏教的な思想では、魂は輪廻転生(りんねてんしょう)していくと考えられています。私の魂は、稲盛和夫という肉体を借りて現世に姿をあらわし、肉体が滅びたとき新たな旅立ちを迎えます。ですから、人生というのは、善きことを思い、善きことを行うことにより、魂を磨き上げるための期間なのかもしれません。現世の荒波にもまれ、自分の魂を磨くことで、生まれたときよりも美しい魂になっていなければ、この世に生まれた価値はないのではないか、と思っています。
※週刊朝日 2013年11月15日号