
「村上春樹」に関する記事一覧



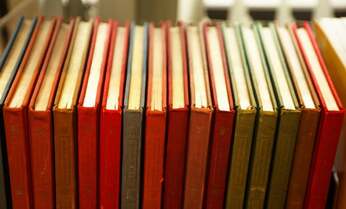


職業としての小説家
村上春樹『職業としての小説家』は、初刷だけで10万部を印刷したり、紀伊國屋書店が大量の買い取りによる新たな販売方法にトライしたりして話題になった。どちらも、日本を代表する小説家「村上春樹」ならではの現象だった。 この本は、タイトルどおりの内容を12回に分け、ほどよい数の聴衆に話しかけるような文体で書かれている。まず小説家とはどんなタイプの〈人種〉なのかを検証し、自身が小説家になった頃をふりかえり、文学賞について持論を語り、表現のオリジナリティーに言及し、それから創作の各論へと移っていく。誰のために、どのように書くのか……小説家を志す者だけでなく、すでに作品を発表している者にとっても貴重な文章が次から次へと現れ、つい赤い傍線を引いたり、その近くに付箋を貼ったりするに違いない。 小説家の端くれである私も、ここで紹介されているいくつかは既に読んでいたにもかかわらず、20カ所ほど付箋をつけた。そうしながら読みすすめるうちに感じたのは、これは、〈個人的な考え方をする人間〉である村上春樹の35年におよぶ実践の書に他ならないというものだった。 〈小説家というのは、芸術家である前に、自由人であるべきです〉 断定を好まない村上が珍しくはっきりと主張し、〈好きなことを、好きなときに、好きなようにやること、それが僕にとっての自由人の定義です〉と書いていた。付和雷同の対極にある個人的な、あくまでも自分の内面の奥底から湧き出てくる考え方を尊重して生きるために、つまり自由人であるために、村上春樹なる小説家は実際にどうやってきたのか。この本を通読すると具体的に理解できる。 自由であり続けるための自律、あるいは決意と開き直りと継続の実践録。それらは、穏やかな口調ながら、創作や小説家に興味のない人にもきっと深い刺激を与えるだろう。
特集special feature
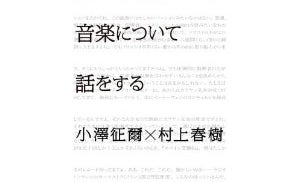

現代ジャズ解体新書 村上春樹とウィントン・マルサリス
巻末に、著者で音楽評論家の中山康樹と、ジャズ評論家・柳樂光隆の対談が載っている。そこで柳樂が「いま『音楽評論家』がいない」と言う。「ライター」はいるが「評論家」がいない。確かにそうだ。私は自分の好きなものについて、同意できてもできなくても、評論が読みたい。実物を見たり聞いたりするより、そっちのほうが楽しいことすらある。 この本は、村上春樹の『誰がジャズを殺したか』と題したエッセイがたくさん引用され、中山さんが感じた共感と違和感を書きながら、どんどん現代のジャズについての考えが四方八方に飛び散っていき、収拾がつかなくなっている。すべては、中山さんの正直な評論家魂によるものだ。この収拾のつかなさがイライラするし、同時に面白いところだ。 そもそも、村上春樹のジャズについてのエッセイが、いかにも村上春樹らしい、読んでいて気持ちいいが、しかしよくよく考えると「結局どうしたらいいんだ!」と肩を揺さぶりたくなるような文章で、その村上に「まあ、(ディジー・ガレスピーのライブを)聴けてよかったけれど、聴き逃したとしてもそれほど悔しくもないだろうな」などと書かれたら、ジャズファンとして何か言いたいと思う気持ちもわかる。ここで「ジャズのことなどわからぬ村上春樹を斬る!」という方向に行かないのが中山さんらしい。村上春樹の気持ちになって、そこから中山さんが考える「現代のジャズについて」が、ジワジワと、的を絞ることなく語られる。 実のところ私はジャズをまったく知らず、中山さんの本を何冊も読んで固有名詞のみ詳しくなっている。それでもジャズファンの一員という気持ちになっている。ウィントン・マルサリスの出現以降、ジャズが「つまらなくなった」とか「燃えない」とか語られているらしいが、このマルサリスはすごく興味深い。でも、文章だけでおなかいっぱいになってしまった。それはいいことなのか悪いことなのか。

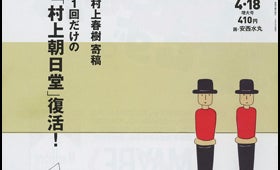


カテゴリから探す
教育・ライフ

NEW






























