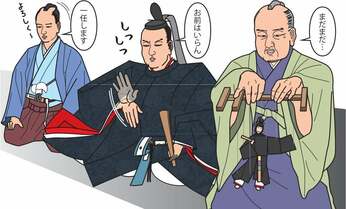真田昌幸、毛利元就、淡路水軍…戦国の山城で「防御力」が高かったのは? 歴史研究家が分析
城といえば、都市部に築城された平城や平山城の印象が強いが、江戸時代以前に築かれた城の大多数は、山城だった。週刊朝日ムック『歴史道 Vol.17』では、城関連の著書も多い歴史学者・小和田泰経氏に自身が訪れた山城を「遺構の保存状態」「防御力」「登りやすさ」「交通アクセス」の4つの基準で採点してもらい、戦国最強で「訪れるべき」山城ベスト50を選出してもらった。ここでは、「防御力」が高かった城をピックアップ。前回配信の記事<訪れるべき「戦国最強」の山城を歴史研究家が格付けランキング!>で戦国最強の山城トップ5を分析したが、それ以外にも防御力が高い城はある。いったいどこか。