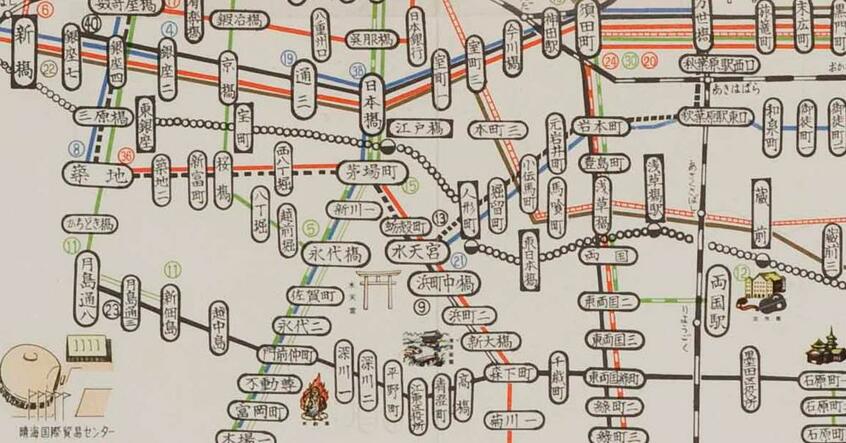
朝のラッシュ時に何台か運転される臨時30系統を狙って、月島川に架かる月島橋上から撮影した。画面右側には今ではあまり見られなくなった消防署の望楼「火の見櫓(やぐら)」が写っている。立派な佇まいは月島のランドマークのひとつだった。隣接する庁舎が東京消防庁・水上消防署月島派出所で、望楼と共に味わいのある建造物だ。余談であるが、火の見櫓は明治期の1887年、お雇い外国人が当局に進言して、このような形態の櫓の建設が始まったとのことだ。
清澄通りが拡幅された1980年代に始まった月島の町の変革。約40年を経て当時の建物が皆無という、無機質にも見える超高層ビル街に変わった。月島橋の東詰めには「月島にはもう超高層マンションはいりません」などとアピールされた看板が掲示されていた。その反面、眺望に優れた「ベイエリア」として居住者が増え、町の発展に寄与しているのも確かな事実だ。現在はここ月島を挟んで築地から豊洲へと卸売市場が移り、これから新たな賑わいを見せるかもしれない。
半世紀前に筆者が見た<都電が走り生活感に溢れた庶民の町>としての風景はもう帰らないが、歴史の歩みとはこういうものだとつくづく考えさせられる。
■撮影:1965年11月11日
◯諸河 久(もろかわ・ひさし)
1947年生まれ。東京都出身。写真家。日本大学経済学部、東京写真専門学院(現・東京ビジュアルアーツ)卒業。鉄道雑誌のスタッフを経てフリーカメラマンに。「諸河 久フォト・オフィス」を主宰。公益社団法人「日本写真家協会」会員、「桜門鉄遊会」代表幹事。著書に「都電の消えた街」(大正出版)「モノクロームの東京都電」(イカロス出版)など多数。








































