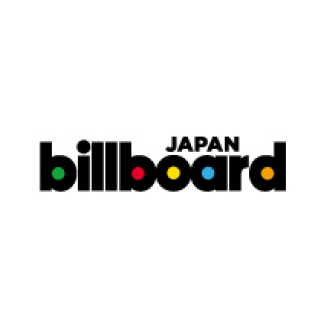2018年7月20日に全米公開された映画『マンマ・ミーア!ヒア・ウィー・ゴー』で、主人公ソフィの祖母=ルビーを演じたシェール。映画公開の1週前、7月13日に先行リリースされた同サントラ盤には、アンディ・ガルシアとデュエットした「悲しきフェルナンド」と、シェールがメインを務めた「スーパー・トゥルーパー」の2曲を提供。当然ながらどちらも完成度高く、あらためて女王の貫録をみせつけた。
本作『ダンシング・クイーン』 は、その映画出演が起爆剤となった、アバのカバー・アルバム。彼らの楽曲のすばらしさを再認識し、撮影を終えた際に「作ろう」と決心したのだという。たしかに、あの2曲を聴けば、ほかの楽曲にも挑戦してみたいと思う、そしてファンに聴かせたいと思うのも納得だ。映画に出演し、ブロードウェイ・ミュージカルの大ファンでもあった彼女が、このアルバムを制作することは必然だったといえる。
「悲しきフェルナンド」は重複しているが、アンディ・ガルシアを除いたシェールのソロ・バージョンが本作『ダンシング・クイーン』では聴くことができる。“自分のもの”にし過ぎて、もはやカバー曲とは思えない。違和感がなさすぎて、セルフ・カバーしたかのような完成度の高さだ。
それは、「悲しきフェルナンド」だけでなく、本作に収録された全10曲すべてが、「アバのカバー・アルバム」ということを忘れてしまうような、オリジナリティに溢れている。それも、彼らの曲に対する愛情と、正しい解釈があるからだろう。そうでなければ、こんなすばらしいカバー・アルバムは作れない。アバの代名詞となった「ダンシング・クイーン」も、誰もがもつ原曲の世界観は一切崩さず、個性を強調し過ぎないような配慮というか、曲への敬意みたいなものを感じる。
アルバムの発売前にティーザー映像が公開された「ギミー!ギミー!ギミー!」も、文句ナシの出来栄え。シェールとは犬猿の仲(?)と囁かれているマドンナが、「ハング・アップ」(2005年)でサンプリングし再燃した同曲だが、これで女王の座も挽回か(?)。ちなみに、2013年にはラッパーのグッチ・メインも「ボブ・マーリー」でネタ使いしていて、後世(若い世代)にも受け継がれる名曲として人気を博している。
「きらめきの序曲」で驚かされたのは、出だしのファルセット含め「まだこんな高音が出るのか!」ということ。劣化を感じさせない安定感もある。1946年生まれ、御年72歳のシェールだが、美貌のみならず、歌唱力も衰えを一切感じさせないとは……さすがだ。次の「S.O.S.」でも、年齢を感じさせないパワフルなボーカルを披露している。Aメロとサビの使い分け・強弱の付け方は、さすがとしかいいようがない。
水を得た魚のように曲との一体感を生む 「恋のウォータールー」 、映画のポップなイメージを取っ払ったアダルティな「マンマ・ミーア」、諭すように歌う包容力抜群の「チキチータ」、1999年の年間チャートを制した、自身最大のヒット曲「ビリーブ」彷彿させるフロア・トラック「ザ・ウィナー」、“聴かせる”壮大なバラード「ワン・オブ・アス」。オリジナル・ソングでも難しいのに、他人の曲を静も動も難なく歌いこなすとは、恐れ入る。シェールが退くことなく、第一線で活躍し続けるのは、努力や研究、音楽や演技への追及を怠らないからだろう。
シェールほどのアーティストが、自ら「カバーしたい」と思わせるアバというアーティスト。あらためて影響力のあるアーティストなんだなと実感した次第だが、彼らの音楽をリスペクトするシェールも、多くのアーティストがお手本とするレジェンドであることは変わりない。そういえば、アバが大ブレイクしていた70年代後期には、自身のシングル「テイク・ミー・ホーム」(1979年)も大ヒットしていた。これらの曲を歌いこなせるのは、そういった時代(ディスコ・サウンド)を共に駆け抜けたから、なのかもしれない。
Text:本家一成