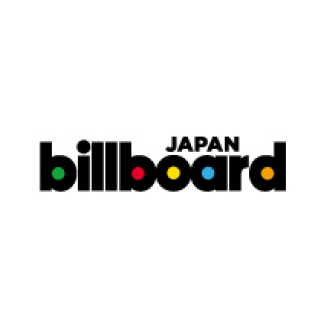さまざまな国の才人が集まるフランス発の音楽フェス【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】。中軸をなすクラシック以外にも大物が見え隠れする。昨年に引き続きアコーディオン奏者リシャール・ガリアーノも登場、今回は徹頭徹尾ソロの完全一人舞台を披露した。
リシャール・ガリアーノ ライブ写真(全3枚)
蛇腹系楽器の巨匠といえばバンドネオン奏者アストル・ピアソラが有名だが、ジャンルの垣根を越えて故郷の(否、世界の)タンゴ界に新風を巻き込んだピアソラが1992年に亡くなって以降、フランスのリシャール・ガリアーノは間違いなく、残された蛇腹ソリスト界隈を牽引してきた一人に数えられる。
ジャズ、ヴァリエテ(フレンチポップ)、映画音楽、クラシック……フランスでは19世紀末以降、ミュゼット(都市部の酒場の舞踏音楽)を彩る楽器としても知られてきたアコーディオンを、ガリアーノは楽器というよりむしろ“一人芝居の俳優の衣装”であるかのごとく自在に操ってみせる。特殊奏法を用いた音響効果も的確に使いこなしながら、ガリアーノも深い愛着を寄せていたピアソラが故郷アルゼンチンの音楽であるタンゴにもたらしたような新風を、アコーディオン・ミュゼットの世界に送り込んだ大物でもある。
「マルゴーのワルツ」、「クロードのためのタンゴ」、いくつかのヒット作も書くプレイヤー=コンポーザー、多面的な顔をもつこの世界的名手が、誰の手も借りずに完全一人舞台で演奏を聴かせる公演は、今回の【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】でも何度かあった――とくに、筆者が接した池袋芸術劇場B1Fでの公演は、ステージがいかにも小劇場(ないし小さな映画館)風といってよい小規模ホールでの演奏だったのも幸いし、まさにモノドラマ(一人芝居)さながらの極上パフォーマンスに仕上がっていた。
そっと舞台に立つや、はじめに繰り出してみせた音は鍵盤ぬき、蛇腹の送風音だけ――黒い内装の劇場内に、海の波音を思わせる独特の音が静かに広がってゆく。やおら弾きはじめた瞬間、幾多のアルバムで知られたガリアーノらしさが立ち現れる。アコーディオンの演奏ノイズまで音楽的に武器にしてしまうような、あの独特のエッジの立った音作り。
ミュゼット、クラシック、ダンス、映画音楽、次々とくりだされるプログラム演目と演目のあいだを、彼はたくみな即興演奏でうめてゆく(折々に大バッハの楽曲からの引用が散りばめてあったのがふしぎと心に残る)。攻めたクラシック楽曲(ドビュッシー「月の光」のようなメロウな曲もあれば、陰影あざやかにラテン情緒を描き出すグラナドス「アンダルーサ」のような難曲もあった)をいかにもガリアーノ風に仕上げてゆく瞬間の連続が子気味好い。縦横無尽、まったく誰の手も借りずに“音によるモノドラマ”をあざやかに演じ進めてゆく。
“モンド・ヌーヴォー(新しい世界)”をフェス全体のテーマに、故郷を離れた地で活躍した作曲家たちの音楽が多く取り上げられていた今年の【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】だが、考えてみればアコーディオンという楽器そのものがフランスではこのテーマと分かちがたく結びついている。19世紀末にアコーディオンをパリのバル・ミュゼット(舞踏場)で流行らせたのは、イタリアから来た移民たちだった――そして実はリシャール・ガリアーノ自身、南仏カンヌで暮らしていたイタリア系の家系に生まれた音楽家でもある。
ガリアーノ本人作曲によるヒット作「クロードのためのタンゴ」で静かに空気を揺らしながら、最後には冒頭と同じく、蛇腹の操作だけで風のような音色を出す演出でしめくくる。その最後の息吹を、ユーモアまじりの所作で演出して去ってゆくガリアーノ……彼自身でなく、彼がもったいぶって舞台に置いていったアコーディオンの方が「息を引き取った」だけで、本当によかった。次に彼の一人舞台を味わえるのは、はたしていつ、どこでだろう。Text:白沢達生