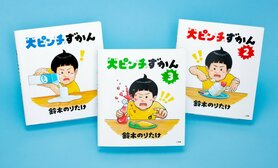当時の資料を見ると、斉彬は毎日天保山に出て、訓練を続ける薩摩兵を指揮していたという。7月8日の発病当日も炎天下に馬上指揮を執っていたが、突然の発熱と腹痛、下痢があった。そしてその死までの1週間容体は悪化の一途をたどった。蘭学をおさめた藩医坪井芳洲は「コレラ」と診断した。
当時、コレラは19世紀三度目の世界的流行期にあり、日本でも数万人の死者が出ている。しかし、コレラによる下痢は発熱や腹痛を伴わず、斉彬の症状には一致しない。芳洲の記録を精読した明治時代の海軍軍医総監高木兼寛は、斉彬の死因を「赤痢」としている。しかし、赤痢に特徴的な血便の記録もない。高熱と解熱を繰り返し意識が時々朦朧としながらも約1週間の経過で死に至っていること、死の前日まで意識が保たれていることから、もう一つ、サルモネラ菌による腸管感染と敗血症、すなわち「腸チフス」の可能性も否定できない。
この時代、腸チフスは世界中にありふれた病気で、上流階級であってもこれにかかることは珍しくなかった。ほぼ同時代にビクトリア女王の夫君サクス・ゴータ・コバーク公アルバート殿下、もう少し前になるが作曲家フランツ・シューベルトは同じように約1~2週間の経過で死に至っている。斉彬の症状からして消化器の感染症だった可能性は高いが、歴史資料から確定診断を得ることは難しいと言わざるを得ない。
ミームを残し
死の前日、斉彬は側近の山田壮右衛門や弟久光を枕頭によび、相続争いを避けるために久光の長男又二郎(忠義)を自分の娘とめあわせ後継者とし、さらに自らの四男哲丸を養子とすることを言い残している。このように周到な手配を終えたうえで、安政五年7月16日未明に逝去している。
しかし、哲丸の夭折、娘と忠義の間に男児が生まれなかったことから薩摩藩主の中に彼の血筋を残すことはできなかった。他の三賢侯は隠居を強いられたとはいえ、井伊直弼暗殺後には復権し藩主の座も息子(養子を含む)が継承している。
子孫が藩主にはならなかったとはいえ、斉彬の開明思想を受け継いだ西郷隆盛や小松帯刀は明治維新にける薩摩藩活躍の原動力となる。ゲノム(遺伝子)は残せなくてもミーム(思想)を残した典型ではなかろうか。