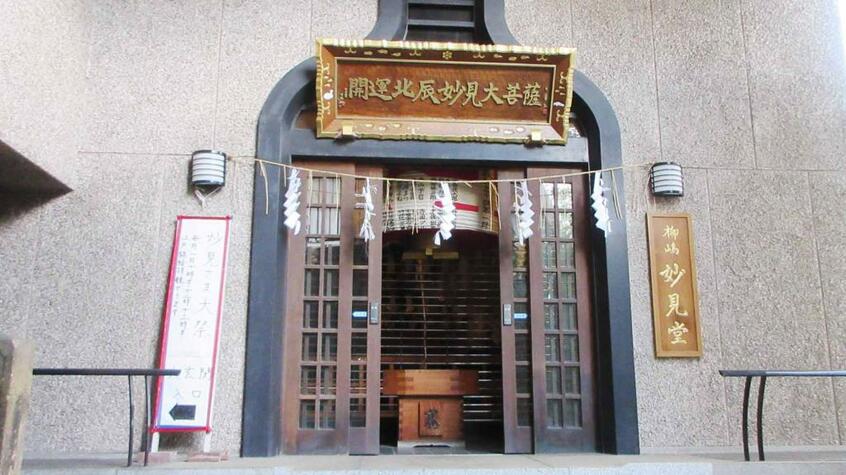

コロナ禍さえなければ、もっと話題になっていい改定が今年あった。オリンピックの年にも本当ならふさわしい話だったのに、コロナにすっかり出足を取られ、見向きもされないので、この際、北斎の誕生日でもある10月31日(旧暦9月23日)にしっかりご紹介しておきたいと思う。
●日本のパスポートが芸術品に
実は2月4日申請分以降のパスポートにおいて、1992年以来28年ぶりとなるデザインが更新されたのだ。残念ながら私の更新はまだまだ先なので、しばらくは実物を目にするのはないだろうと諦めていたら、友人が更新したと聞いて早速みせてもらった。使用するページのすべてに、葛飾北斎の「冨嶽三十六景」のうちの24枚が描かれていて、スタンプを押してもらうのがもったいないほどの出来栄え。友人も海外への渡航が現在のように制限されている中で更新するかどうか悩んだらしいが、「手続きも一部は自宅のパソコンでできるし会場も空いていていつもよりラクだった」と聞いてうらやましさが倍増した。
●富士山が各ページに描かれる
もちろん図案には一番有名な「神奈川沖浪裏」も含まれているが、この24枚の選定にはさぞや頭を悩ましたことだろう。今でも有名な観光地からの富士山の眺めは、オリンピックで海外から訪れる観光客の目もきっと引いたに違いない。日本には、富士山をはじめとした山を信仰の対象とする文化が、古代から脈々と続いている。古社の中にはご神体が山である神社は多いし、お寺には「山号」(寺院の前につける別称)が必ずついている。山につけられた名前は、その土地が持つ歴史を語る場合も多く、小さな山にさえ祠が祭られているのをよく見る。
●世界が驚いた北斎の波の絵
今でも土地の吉兆を占う際、地域の霊山が見える場所は“縁起がよい”と判断される話をよく聞く。そういう意味からも、富士山が眺められる場所というのは、江戸時代の人たちからすればよい土地の証だったのだろう。「冨嶽三十六景」と銘打ってはいるが、よく見ればその画面の中に働く人々の姿が細かく描かれている。ただの風景画ではなく、実際に目にしたその瞬間の土地の姿を紙に写し取った写真のような浮世絵なのである。「神奈川沖浪裏」などは波の間に浮かぶ二隻の船の中で、必死に櫓を漕ぐ舟人たちの姿が見える。いったい北斎はこの様子をどこから見ていたというのだろう。




































