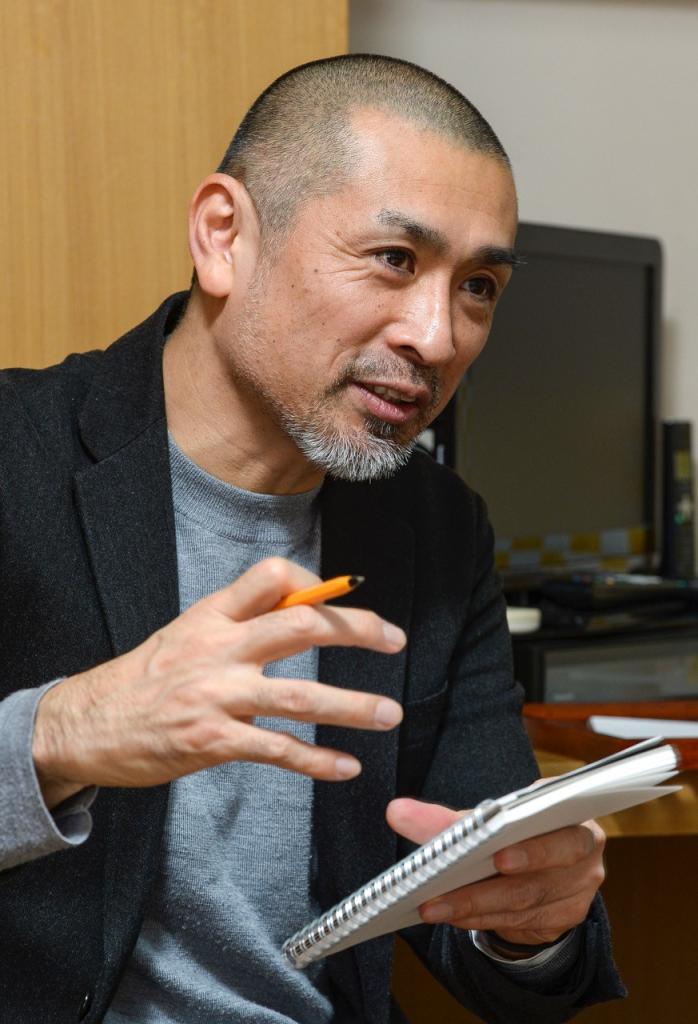
福岡 でもいくら隠しても厳然としてピュシスの領域はあるので、現在ピュシスとしてのウイルスが猛威を振るっているわけです。ロゴス化されすぎた人間への警鐘です。その言語化できない警鐘に対して、耳を澄まし、目を凝らし、我々人間がロゴスとピュシスのあいだにしか生きられない生物であることにもう一度注意を向けようというのが、「ピュシスの歌を聴け」という言葉の意味です。
■人間は、子どもの時期が異常に長い
おおた 具体的にどうやったらピュシスの歌を聴けるようになるのでしょうか。
福岡 端的に言えば、子ども時代を思い出そうということです。子ども時代は五感が研ぎ澄まされている。エロスから無縁でいられる。人間だけが与えられた特別なモラトリアムですよね。
おおた 生殖をしなくていい、食料もまわりの大人がとってきてくれる、遊んでいるだけでいい子どもの時期が、人間は異常に長い。一般的には未熟な時期をいかに短期間で通過するかが生物のサバイバルの鉄則なわけですが、人間はその逆に進化した。そこで知的な飛躍が起きたというネオテニー(幼形成熟)理論ですね。
福岡 子ども時代はロゴスが未発達な分、非言語的な能力が研ぎ澄まされています。そのときにさまざまな「センス・オブ・ワンダー(神秘さや不思議さに目を見はる感性)」を経験するわけです。これがすべてピュシスの歌を聴いている時間です。私の場合、昆虫少年で、ルリボシカミキリの青さに驚いたり、アゲハチョウの変態に目を見張ったりしたわけですけれど、むしろですね、私の指先に残っている感覚は、痛みです。
おおた 痛み?
福岡 たとえば、小学3年生くらいのとき、クモの巣にハチが引っかかっているのを見つけました。助けてやろうと思ったら、ハチに刺されました。ミツバチでしたから、一度刺すと死んでしまいます。クモの巣は壊れてしまいました。私もすごく痛い。みんな不幸な結末になったんです。自然に介入することがいかに愚かしいことかと、痛みとともに学びました。




































