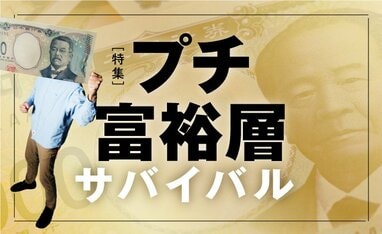「こうした政策の結果、スウェーデンの成長率や生産性・国際競争力はOECD平均をかなり上回り、アベノミクスができなかった『成長による分配』を達成しています」(同)
スウェーデンでは国民も政治家も経済危機という手痛い経験を経て、財政規律を守るのが福祉国家を守る前提条件だということを理解したのが改革の原動力になった。だが、90年代にバブル崩壊を経験した日本では、いまだに改革は不発のままだ。
「安倍晋三元首相は安保法制や改憲に強い関心を示す一方、痛みを伴う改革には本気で取り組まなかった。岸田文雄首相も同じだと思います」(同)
政治家は支持者の顔色をうかがい、官僚は政権に忖度する。選挙を意識して短期志向となり、積極財政はばらまきがちになる。子どもや将来世代に負担が転嫁される、と田中さんは悲観する。
分配重視というならば、まず取り組むべきは社会保険の見直し、特に過去一貫して増大した「逆進的な保険料」の是正だと田中さんは言う。基礎年金の支給額は今後30年で3割減(所得代替率)との予想も出ているが、厚生年金の報酬比例部分はほとんど減らない見通しだ。
「年金財政が苦しいため給付金を削るのはやむを得ないと思います。でも、基礎年金しかない人たちの支給を主にカットするのはあまりにひどい」(同)
■貧困の高齢者が増える
雇用者の約4割を占める非正規労働者は十分な年金給付を受けられない。近い将来、貧困の単身高齢者が増えるのは確実だ。
別の見方もある。
「そもそもアベノミクスで所得格差が広がったという認識が誤りです。各党が分配政策を公約に掲げたこと自体、私はナンセンスと受け止めています」
こう語るのは第一生命経済研究所の永濱利廣・首席エコノミストだ。所得格差を示す「ジニ係数」。より実態に近い「再分配所得ジニ係数」は05年をピークに緩やかに下降トレンドが続く。
「日本では手厚い社会保障制度で再分配機能は作用しています。問題は豊かさを感じられないこと。それはパイの拡大が足りないからです」(永濱さん)