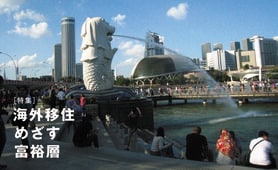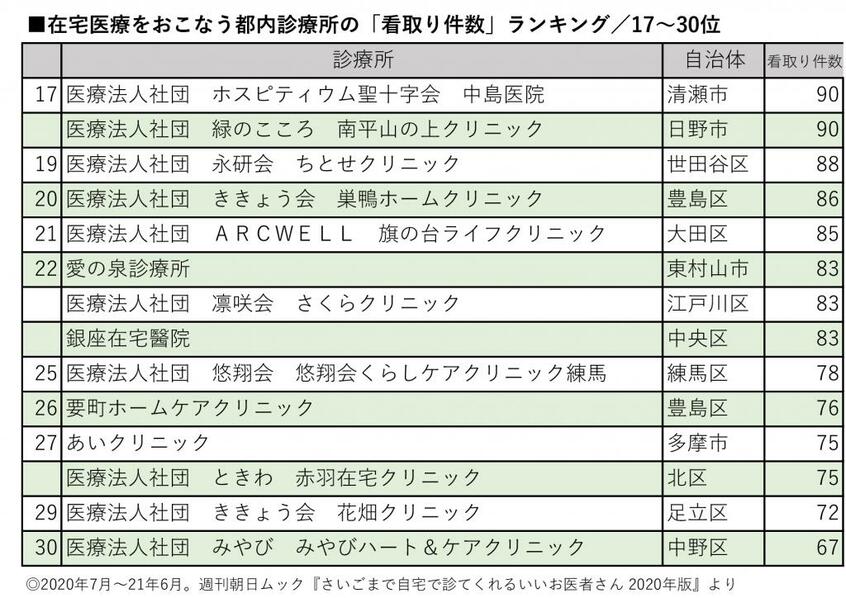
そうした経験を踏まえ、在宅医療の意義をこう語る。
「町の先生も、長年見てきた患者さんが限界だと思ったら、ちゃんと外来で伝えなければいけないと思うのです。うまく食べられなくなってやせ細った高齢者の人が急に倒れて、家族に救急車を呼ばれ、救急隊員に心臓マッサージされて、大きな病院に運ばれて、警察医に遺体を検案されるのは、ちょっと理想とは違うかもしれないですよね。そうではなくて、町の先生と連携して、どうすればこの人が残りの少ない時間を家族と一緒に楽しく過ごせるかを考えるのも、我々の仕事です」
■「大病院と町医者のすみわけ」カギになったコロナ禍
同クリニックはコロナ禍においてもさまざまな在宅診療をおこなってきた。荘司医師は立川市医師会のワクチン担当理事を務めたが、そこで地域包括ケアの真価が試されることになったという。その事例の一つが、外出が難しい高齢者のために、在宅でのワクチン接種の体制をいち早く21年5月中旬に整えたことだ。
「65歳以上の接種が始まるとなったときに、まずは各クリニックの接種開始日を決めましたが、その次は心疾患などで重症化リスクの高い人や、在宅医療を受けていて外出が難しい人に優先的にワクチンを接種するように決めました。そしてその次は、やはり重症化リスクの高い透析患者の人たちが普段通っている透析病院で接種ができるよう、各病院長に呼びかけ、計画を立てました」
6月下旬から始まった「第5波」の渦中でも、「大病院と町医者のすみわけ」がカギになった。
「多摩地区の医療はなんとか耐えきりました。立川には災害医療センターという三次救急(重症・重篤患者に対して高度な医療を行うこと)の病院があり、最初はどんな患者でもまず入院させていました。しかし感染者数が多くなると、ベッドの数が足りなくなってきました。そこで軽症の人を我々が在宅で引き取り、空いたベッドを往診で診てきた中等症以上の人にゆずることにしました。病院と町の診療所が普段からやりとりして、電話一本で連携できるようにしていれば、入院が必要な患者が入院できないということはなかったと思います」
在宅の患者を支え、地域医療を支える在宅医。このコロナ禍を、荘司医師はこう振り返っている。
「入院調整もワクチン接種の順番も、大病院と町医者がそれぞれの役割を果たして連携することが大事なのだと本当に思いました。このコロナ禍は『地域包括ケアの究極の実験場』だったと思います」
(白石圭)




![さいごまで自宅で診てくれるいいお医者さん[2022年版] コロナで注目! 在宅医療ガイド (週刊朝日ムック)](https://m.media-amazon.com/images/I/51vcJsRbQwL._SL500_.jpg)