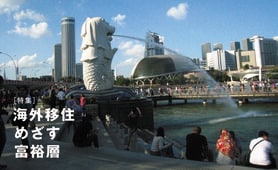院長の荘司輝昭医師は、一日10件前後の家に車で訪問する。厚生労働省は病院から半径16キロ圏内に出向く診療を「在宅診療」と定義づけ、保険点数の加算対象としているが、立川在宅ケアクリニックの半径16キロには吉祥寺、立川などといった人口が集中する街も含まれている。
限られた医師で、24時間365日、多摩地区の幅広いエリアをカバーする往診対応をどう工夫しているのか。荘司医師はこう話す。
「家族をいかに味方につけるかが一つのポイントだと思っています。家族全体が在宅医療に慣れれば、急な症状変化にも自分たちで対応することができる。そのためには『家族の力』を高めるのが一番必要なのではないかと思っています」
たとえば、昼間の往診で疼痛コントロール(がんによる痛みに対する治療)ができていれば、夜間の緊急往診数は少なくて済むと荘司医師は言う。
「手術や大きな検査を除き、末期がんの人の痛み止めなどの治療は在宅医もおこなっています。ですが医師は家族の代わりにはなれません。患者のそばに24時間いるのは家族です。がんや心不全、呼吸不全の末期で、夜に苦しい症状が出ると、家族は心配して医師に電話することがあります。でもそこで、この薬を使ってみてくださいと言ってみると、症状が落ち着いて電話が来なくなることも。昼間、家族を含めて患者への対応がちゃんとできていれば、家族が不安になって医者を呼び出すこともなくなってきます」
■残された時間を伝えないと、家族が最期を見届けられない
また在宅医として、残された時間がどのぐらいかを患者に伝えることも大事な仕事だと語る。その背景には、警視庁の嘱託医として勤めてきたなかでの苦い経験がある。
「ある大学病院の先生が『次に来たときはホスピスのことも考えないといけないね』と言って帰した患者さんが、その翌日に亡くなり、私が警視庁で検案(検視)したことがあります。ご遺族と話すと、『昨日病院に行ったときはまだ大丈夫って言われたんです』と。でもその患者さんは、私が見たところでは、がん末期でいつ亡くなってもおかしくなかった。医者も患者から見放されたと思われるのはつらいから、短い外来の時間で最期について話すのは難しいのだと思います。だけど伝えないと、家族が患者の最期をちゃんと見届けられなくなってしまう。だから“大病院と町医者のすみわけ゛が重要なのです」