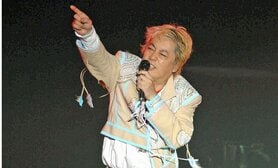そもそもなぜこんなにキリンの移動が多いのかと言えば、繁殖のためだ。
コロナ禍で近年は減っているが、例年20件程度は国内でキリンの引っ越しがあると教えてくれたのは、多摩動物公園の飼育員・清水勲さん。キリンを担当して22年目のベテランだ。
多摩動物公園は国内でキリンを一番多く飼育していて、全国193頭(2021年12月末時点)いるキリンの血統管理を担う。近縁な関係にある個体同士の繁殖を避け、遺伝的な多様性を保つためだ。各地の動物園から「オスが欲しい」「メスが欲しい」などのリクエストがあれば、適した組み合わせを分析して調整をする。

■移送中に命を落とす
「体が大きくなると運ぶのが難しく、ストレス耐性もなくなるので、原則として3歳前後までに移動するようにしています。暑さや寒さで負担をかけないよう、引っ越しは春と秋に集中します」(清水さん)
大きいわりに繊細なキリン。今年4月には、王子動物園(神戸市)の「ひまわり」が岩手サファリパーク(岩手県一関市)への移送中に命を落とす事故も起きた。輸送箱内で体勢を変えようとして転倒し、呼吸不全に陥ったのが原因と公表された。
移送以外にも、金網に角が挟まって抜け出そうとして頚椎(けいつい)を損傷するなど事故死が少なくない。だが、死亡原因の多くはキリンの蹄(ひづめ)の伸びすぎだ。
前出の高嶋さんにとって忘れられない「ユズ」(13年に多摩から盛岡市動物公園に移動)が17年に死んだときも、蹄が伸びて関節症を起こしたことが遠因だった。動物園で暮らすキリンは、野生と違って運動量が少なく蹄が伸びやすい。蹄が伸びると歩き方に影響し、関節が悪化して立てなくなり、死に至る。
かつてはそれが寿命で、しかたのないことだと思われていた。体重が1トン近くもあるキリンの足を押さえつけて蹄を削ることなど到底無理だからだ。
ところが、今では多くの動物園で蹄のケア(削蹄)ができるようになり、寿命が延びている。可能にしたのがハズバンダリートレーニング。削蹄のために足を出したり、採血のために首を曲げたりなど、健康管理に必要な動作を動物が自主的にするようにご褒美を与えながら訓練する方法だ。