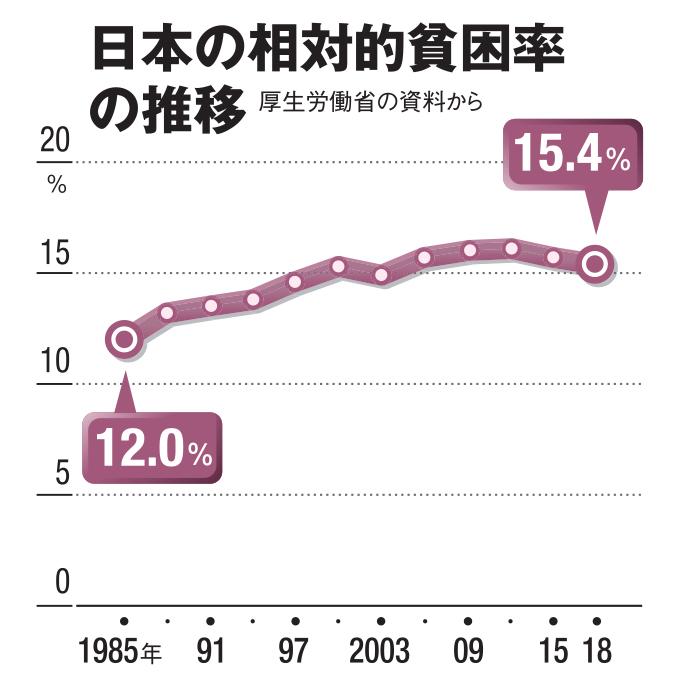
■自己責任で切り捨てれば、社会にとっても大きな損失
同プロジェクトは無料。就労支援のプロたちが3カ月にわたり、自分の強みの把握から始め、履歴書などの書き方、面接のコツ、メイク術などをオンラインで教える。昨年は全7回開催し、延べ311人が受講。給料が上がったり、パートから正社員に採用されたりした人たちも出た。
「自分でその道を選んだんだろうと、貧困を『自己責任』で切り捨てれば、社会にとっても大きな損失です。稼げるようになれば家計の安定につながり、個人消費にも貢献し、社会保障の担い手にもなり経済全体にとってプラスになります」(渡辺さん)
コロナ禍で可視化された貧困は、物価高の影響もあり悪化することも考えられる。国に求められる対策は何か。東京都立大学の子ども・若者貧困研究センター長で、同大学の阿部彩教授(貧困・格差論)は言う。
「まず求められるのは、正社員として雇用するよう雇用構造を変えることです。貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)にいる母親は、子どもが独立しても貧困の状態が続きます。正社員として雇用されれば、社会保険料の問題もなくなります。加えて、児童扶養手当の支給額も引き上げるなど、制度を根本から見直すことも重要です」
日本女子大学の周燕飛(しゅうえんび)教授(労働経済学・社会保障論)は、労働所得は母子世帯の総収入の約8割を占めていることから、シングルマザーの稼ぎ力を高めることが何より大切だと言う。
「そのためには、学び直しへの支援や、キャリアカウンセリングの充実などが求められます。また、シングルマザーに良い就業機会を増やすことも重要です。家庭の事情で退職した社員の再雇用を制度化する企業への支援や、中途採用の門戸を広げるための人材マッチング支援は、その具体策として考えられます」
もちろん、仕事と家庭の両立ができなければ、シングルマザーの稼ぎ力を収入と結び付けることができない。まずは、正社員の「しんどい」働き方を変えることが先決となると指摘する。
「そのほか、養育費の確保、貧困の連鎖を防ぐための子どもへの学習支援、ディープ・プア家庭への緊急支援なども引き続き検討すべきです」(周教授)
(編集部・野村昌二)
※AERA 2022年8月29日号より抜粋








































