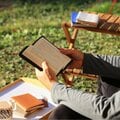もう生きていたくない──。思いの吐露が、現代人が毎日のように触れるSNSで、増幅されてしまうことがある。起こりうる負の連鎖とどう向き合うか。AERA 2023年1月23日号から。
* * *
ICT分野の市場調査やマーケティングを行うICT総研によると、国内のSNS利用者は8千万人を超え、普及率は82%にのぼる。自殺問題などを取材するジャーナリストの渋井哲也さんは、インターネット掲示板が主流だった頃と比べて、「死にたい人」同士が出会いやすくなったと指摘する。
「以前は死にたい感情を言語化できなかった人は掲示板にたどりつけなかった。今は、『親がうざい』『つらい』などの言葉からアクセスできるので、よりライトにつながれるようになりました」
■「死にたい」の悪循環
SNSと希死念慮に相関はあるのか。自殺予防が専門の和光大学現代人間学部の末木新(はじめ)教授は、希死念慮(きしねんりょ)を持つ者が相談しあうことで自殺を防げるという仮説を立てたことがある。
だが、それは幻想だった。
「ネットで自殺方法を探せば死にたい気持ちは強まり、匿名の誰かに相談しても状況はむしろ悪くなってしまうことがわかりました。『よくなるといいな』と思っていた僕が見ても、そうでないと判断せざるを得なかった」(末木教授)
他人に相談したことで癒やされたり、アドバイスすることで救われたりと、個別で見ればいい影響が出たケースもあった。ところが、全体的な傾向はネガティブなものだったという。
たとえば、こんな負の連鎖も起きていた。
「メンタルヘルスの状態が悪くなると、インターネットの利用量が増えるという関連も見られました」
死にたいと感じた人がネットで自殺方法を検索したり、誰かに相談したりする。それによって希死念慮や抑うつ感が高まり、ネットの利用がさらに増える。死にたい気持ちが強まる……。
希死念慮や不安感を持つ人をサポートする東京メンタルヘルス・スクエアのカウンセリングセンター長の新行内勝善さんは、著名人の自殺があった際などSNSで自殺に関する情報が増えそうなときは、相談者にこうアドバイスしている。