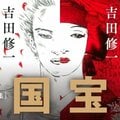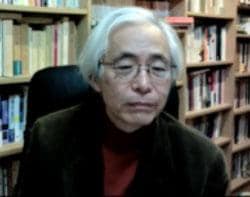
たしかに社会上層部の男性はまだ優位性を維持しようとしています。しかし、西欧ではそれは男性全体の意思ではない。高等教育を受ける女性が多いのは、娘の教育をだいじだと考える父親がいるからでもあります。
女性のいらだちは、女性が置かれた社会的な条件も原因になっています。女性の生きる環境はとても複雑になりました。高等教育を受けたり、興味深い仕事に就いたりする機会は増えました。その一方で、子どもを産む機会も変わらずにある。
加えて、女性解放が進む今は、経済が傾き、生活水準が落ちている時代です。
このいらだちがすべての女性に見られるわけでもありません。知的な環境で生活している人、大学人といった立場にある女性によく見られます。それは古典的なプチブルジョアに特有の満たされない思いでもあるのです。今やプチブルジョアとは男性だけではありません。
もちろんまだ残っている男性優位についてのいらだちもある。けれど、社会階層がはらむ問題と混同している部分もあるのです。
フランスや米国などで、対決的なフェミニズムを担っているのは、経済界などの上層にまだ残る支配的な男性に怒っていて教育水準が高いプチブルジョアの女性たちなのです。
──今のフェミニズム運動とともに広がった「ジェンダー」という用語に批判的ですね。
「ジェンダー」は「性」という言葉と置き換わったけれど、意味が流動的で現実をうまく捉えられない。ピューリタン革命みたい。この言葉は、性的なことを連想させませんからね。(構成/ジャーナリスト・大野博人)
※AERA 2022年1月31日号より抜粋