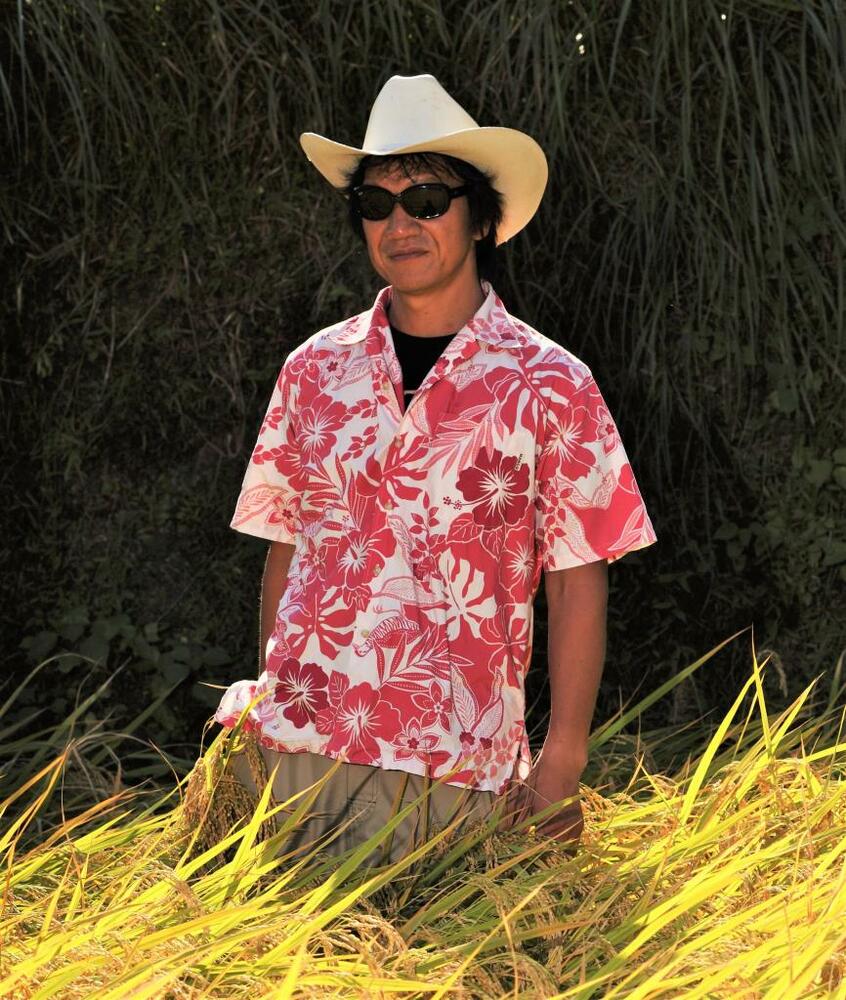
読み始めてすぐに分かった。自分はそもそも、句読点(テンやマル)の使い方もなっていなかった。語順も、気分で、適当に書いていた。
<テンの打ち方や語順のような、義務教育段階からして原則を知る必要のある問題については「適当に」ですまされてきた>
著者はそう書く。わたしたちは義務教育でそれなりの時間をさいて国語教育を受けてきた。作文を書かされ、基礎的な国語文法も習った。しかし、句読点、なかんずく、読点(テン)をどこに打つべきか、原則を教わった記憶はない。原則を語れる教師がいなかった。同様に、段落変えはいつするのか、これも教わっていない。
いまと違って文学作品はそれなりに教科書に載っていた時代だ。名作を読んで、各自「適当に」学ぶ。そういう“教育方針”だったと言われても仕方がない。それでは教育ではない、教育放棄なのだが。
著者は、文学ではなく、「作文」技術の原則に徹底してこだわった。
<言葉の芸術としての文学は、作文技術的センスの世界とは全く次元を異にする。>
人は、文章を作ることで生きている。生きるとは、作文することだともいえる。学校にいるならば宿題に論文、社会人になれば、メール、企画書、稟議書、礼状に詫び状。公に発表すると否とにかかわらず、わたしたちは、日々、文章を組み立てることで生きている。そのくせ、作文技術の大原則は教わっていないのである。本書が長く読み継がれている理由も、そこにある。
名文を書こうというのではない。分かりやすい文章を書く。そして、分かりやすい文章は、簡単ではないのだ。語順にも、助詞の選択にも、しかるべき決まりがある。そこを、「なんとなく」ではなく、あくまでも論理で説明しているのが本書だ。
だから、<「日本語は論理的ではない」という俗説>に対する筆誅は、峻厳である。ここで事々しくウィトゲンシュタインを引くまでもないが、そもそも論理的でない言語など、あるはずがない。欧米の言語であろうと、日本語、中国語であろうと、あるいは“未開”社会の言語であろうと(ここでなぜ“”ひげ括弧を使っているかについては、本書をぜひ参照されたい)、それぞれに論理の筋道が通っている。それぞれの生活様式にしたがって、「言語ゲーム」が成立している。論理的でない言語などという、非論理的なことがあるはずがない。

































