
DiGAROでは、リアルでもデジタルでも楽しめるよう、高画質プリント作品の展示に加え、スマートフォンで鑑賞するAR(拡張現実)展示も併設する。自宅などからオンラインで作品を見ることもできる。
課題はデジタルアートをどう売っていくか。ネットではコピーし放題。個展でプリント作品を売るなどしなければ、アーティストにお金が入らない。これでは継続的な活動はしにくい。
問題を解決すべく編み出したのが「ギャランティカード」という仕組み。作品のオーナーにチップやQRコードを組み込んだカードを発行。スマートフォンをかざして作品にアクセスする。さらに関連グッズやプリント作品が売れると、収益の10%をオーナーに還元す
る。
■オーナーがパートナー
オーナーには新たな才能を発掘する楽しみとともに、継続的に収益を得る機会も提供する、というわけだ。ただ、デジタル作品は著作権など法的権利があいまいな面も否めない。このカードを共同開発したITベンチャー「canow」の大坂亮平COO(39)は、デジタル作品の普及には決済と所有権に関する法整備が必要と唱える。
「デジタル作品の『一点もの』に関する扱いを、現実世界の絵画と同じにしてもらいたい。それには、ギャランティカードやNFTといったシステムで取得したデジタルの権利も法律で認めてもらえる制度が必要です」
NFT(Non-Fungible Token)とは、ネット上で「固有の価値」を証明する技術。デジタル作品を取引する場合、NFTを組み込んだ作品なら、コピーでなくオリジナルだと「お墨付き」が得られる。デジタル作品にも価値を付けやすくなるため、海外ではNFTを使った高額取引が相次ぐ。
代表的なのはTwitterの創業者ジャック・ドーシー氏が2006年3月21日に投稿した初ツイート。今年3月に291万ドル(約3億円)で落札された。それは「一点もの」としての価値が認められたからだ。
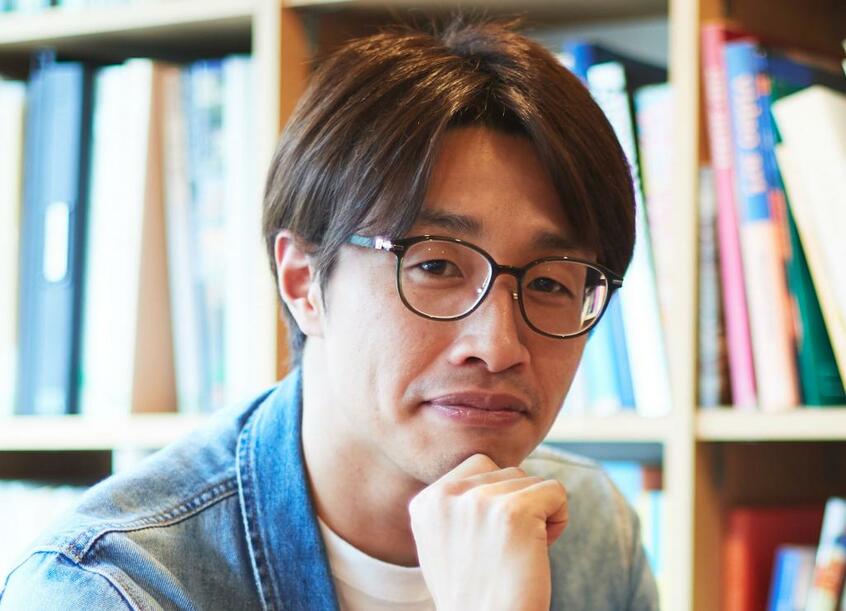
「NFTが普及すればデジタル作品の流通が促され、ビジネスとしての可能性も広がります」
と野呂さん。DiGAROでも導入したい意向だ。ただ扱う作品の相場は20万円ほど。海外のような高額取引は想定しない。「富裕層が投機に走る今の動きはバブル的な要素もあり、長続きしないと見ています」
有楽町に実店舗を開いたのも、デジタルアートを身近に感じてもらうため。近くは有名画廊が軒を連ね、幅広い層の美術ファンに作品に触れてもらう。オープン記念のグループ展(今月1~20日)は、海外ファンが多いアーティスト5人の計15点を展示。若者だけでなく中高年も訪れた。野呂さんは意気込む。
「日本のアート・カルチャーを世界に広めるために多くの仲間と事業を展開していきたい」
(編集部・渡辺豪)
※AERA 2021年6月28日号







































