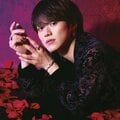巨大グルメサイト「食べログ」は、ユーザーからの口コミレビューを独自のアルゴリズムで点数化している。評価点の問題で裁判となるほど、飲食店側もユーザー側も“点数”を重要視している。しかし、「食べログ」が影響力を高めたことにより変化した構造も問題視されている。タグ付け社会と点数文化を読み解く。AERA 2022年7月11日号から。
* * *
飲食店側もユーザー側も“グルメサイト離れ”が進んでいるという指摘もある。
グルメブロガーのフォーリンデブはっしーさんいわく、「SNSの台頭で情報の探し方は真逆になった」。以前はエリア→お店→料理と絞っていって何を食べるか決める流れだったが、今はインスタグラムなどSNSに流れてきた一枚の料理の写真に目を留めて、その店がどこにあるのか探して行ってみるという具合だ。
食べログも、おそらくこういう逆風を認識しているだろう。苦戦を強いられる中で、いかに信頼を回復していくか。今後の動きが注目される。
食べログ側の課題だけではなく、使う側の課題でもあると指摘するのは、著書『過剰可視化社会』を5月に刊行した評論家の與那覇潤(よなはじゅん)さんだ。
與那覇さんは、社会の「失敗に対する許容度」が下がっていることも、食べログの普及に関連しているのではないかと言う。
食べログを店選びを失敗しないために使う、という人は多いだろう。初めての店に入る前に評価を確認し、点数の低い店は避ける。会食や接待に使った店がいまいちだったときも、「いやぁ、食べログでは3.5だったんですけどねぇ」と言えば言い訳が立つ。
「それは言い換えれば、偶然性が持っている価値が見失われているということです。『ちょっと店を外しちゃった』というのは許されない。『たまたまこうだった』というあり方に対して、寛容でない社会が生まれているんだろうなと思います」
事前にあらゆるマイナスを排除する。それが本当に“成熟”した社会のあり方なのか。