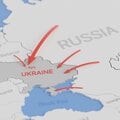とある地方都市で小さな命が失われた、あの衝撃的な事件を私が知ったのは2016年の初夏のことだった。
朝日新聞・特別報道部の記者を中心とする取材班では、それまで1年以上かけて児童虐待の実態に迫ろうと地道な取材を続けていた。特報部のデスクになったばかりの私から取材班に呼びかけ、今後の取材方針を話し合う会議を開いた。そこで、取材班のリーダー的存在だった座小田英史記者が、取材に着手しつつあった10以上の児童虐待事件の概要をA4の紙2枚にまとめ、渡してくれた。
そこに書かれていた事件の一つから、私は目が離せなくなってしまった。
<母親が、恋人との時間を優先するために子どもを川に投げ落として殺す。裁判では突き落とす際に、長女が「ばいばい」と笑顔でいた様子が……>
実際に起きた事件の初報は、社会面1段見出しのいわゆる「ベタ記事」。地方版には続報が何回か掲載されたが、社会的な関心を集めた事件ではなかった。それにしても、なぜ川に? 親や施設に預けることはできなかったのか? 恋人はどうしていたのか? そんな状況になる前に、誰一人として母子に救いの手をさしのべることができなかったのか?……ベタ記事ではわからない、いくつもの「?」が次々に頭に浮かび、会議は上の空。そして気づくと記者たちにこんな指示を出していた。
「この母子が橋の上に追い詰められるまでに何があったのか、取材で徹底的に浮かび上がらせてほしい」
取材にあたったのは、虐待や児童福祉問題の取材経験が豊富な山本奈朱香記者や山田佳奈記者ら。母親は服役中だったため、裁判記録と関係者の証言だけが頼りだ。地方総局の協力も得ながら裁判記録を丹念に繰り、親族ら母子の関係者に片っ端から取材を試みた。足を泣かせながら関係者を回る取材を、新聞社では「地取り」と呼ぶ。相手にたどりつけなかったり、取材を断られたりと、「空振り」が延々と続くことが多い、とても効率の悪い取材だ。
それでも記者たちの粘り強い取材で親族や医師から貴重な証言が得られ、母子の暮らしぶりが少しずつ見えてきた。母親が育児の悩みを行政に相談していたこともわかった。それでも、ストレスで追い詰められた母親はその夜、預ける先を見つけられずに「この子がいなくなるしか……」と思い詰め、橋へと向かった。