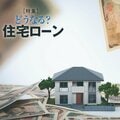日本銀行は2026年初頭に利上げを再開し、26年中に政策金利は1%台に乗せるとの見方も出始めた。日銀の利上げ見通しを受けて、住宅ローンを抱える人の返済負担が増加するのは必至だが、その負担を軽減する策はあるか。
【図表・住宅ローンシミュレーション】これから変動金利が上がったら返済額はどうなる?
「まず、借り換えを考えるべき」
そう話すのは、住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営する塩澤崇氏だ。
「特に地方銀行の変動金利の住宅ローンを利用している人ならば、借り換えによって金利を大幅に引き下げられる可能性があります。2018年以前にローンを組んだ人ならば、現在1.2%前後の金利が適用されているのですが、直近のSBI新生銀行は0.590%で、PayPay銀行の最優遇金利は0.6%。半分に引き下げられる余地があります」
変動金利は政策金利と連動しやすいが、厳密に言えば、3つの要素で各金融機関が設定する住宅ローン金利は変わる。
1つ目は、調達金利。貸し出しのためのお金を調達する際に発生するコストだ。銀行間での短期的な資金取引に適用される金利の基準となる日銀の政策金利や預金金利が、この調達金利に相当する。
平均年齢が上がると保険料が増える
2つ目は、オペレーションコスト。店舗や人件費なども含め、金融サービスを提供するうえで発生するコストが増えるほど、金融機関は住宅ローン金利を引き上げる傾向にある。
3つ目は、団体信用生命保険(団信)だ。ご存じのとおり、ローンの契約者が亡くなるなどの不測の事態に陥った際にその後の返済が免除される保険で、銀行が生命保険会社に保険料を支払う。債務者の平均年齢が上がると保険料が増えるため、そういう銀行は金利が高めになりがちだ。
「ローンを借りないと入れない点やそのときのローン残高相当額が保険金として支払われるといった点が通常の生命保険と異なりますが、健康不安リスクの低い若い人ほど保険料が下がる点は同じです。そのため、長く住宅ローンを提供しているメガバンクや地方銀行ほど、ローン契約者の平均年齢が高く、保険料負担が大きくなりがち。逆に、ネット銀行は若い契約者が多く、保険料負担が小さい。だから、手厚い保障の団信を無料でつけているところが少なくない。店舗がないネット銀行はオペレーションコストも抑えているため、さらに有利な金利を提示している傾向にあります」(塩澤氏)