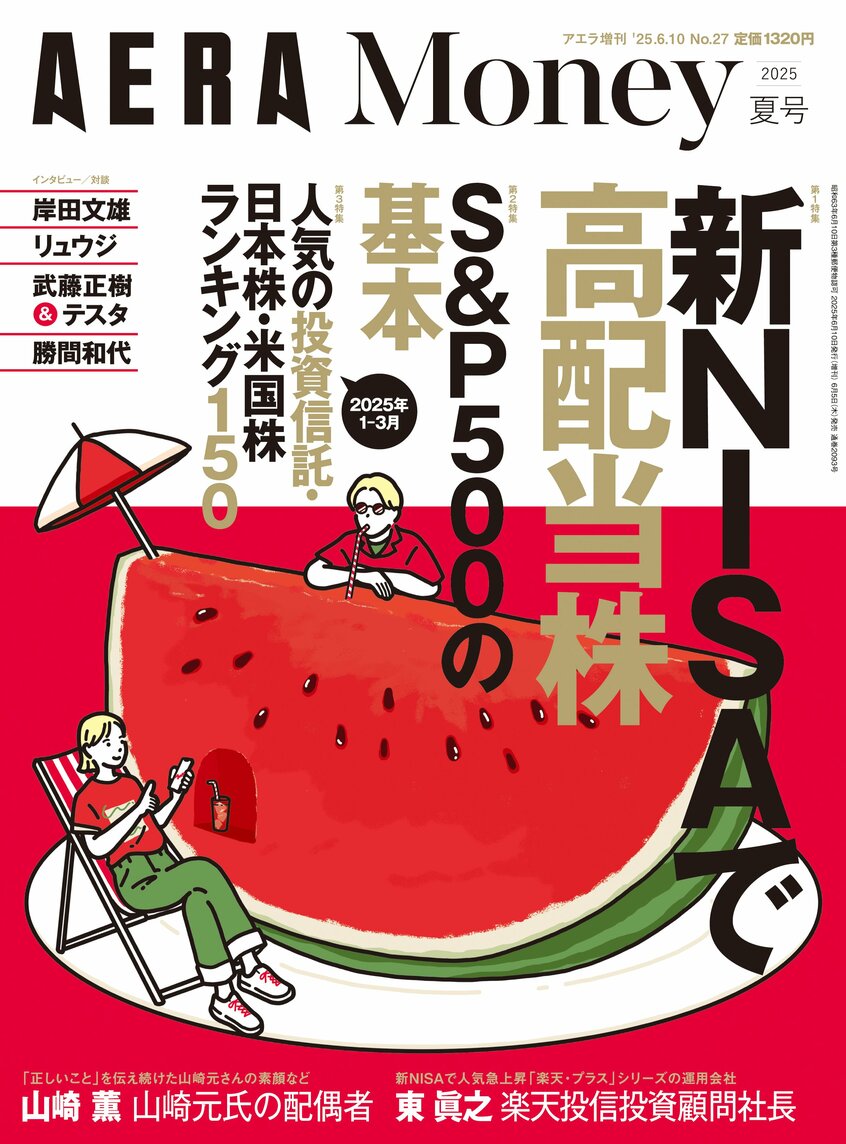
配当性向の割合が高いことで知られる一つが製薬株。
生活日用品の販売比率が高いアース製薬の配当性向は61%、小林製薬は74%(ともに2024年12月期決算短信の2025年12月期予想)。
武田薬品工業に至っては262%(2025年3月期第3四半期決算短信の1株当たり予想配当と1株当たり予想当期利益から算出)に達している。利益の2倍以上を配当に回しているということだ。
「同じ業界で配当利回りが同水準だった場合、配当性向が低いほうが今後、さらに利益の中から配当を増やせる余力が高い。
つまり同じ業種なら『配当利回りが高いのに配当性向が低い』ほうが増配余地があるという見方もできます」
配当性向とDOE
次に「DOE」の意味と見方について教わった。
「DOEは株主資本の何%を配当に回しているかを示す指標です。
個人で言うなら、配当性向は1年の家計からどれだけ配当に回しているか。
DOEは自分の貯金や持ち家も含めた資産の中から配当をどれだけ出しているか」
わかりやすい。
配当政策の目標値としてDOEが好まれるのは配当性向に比べてブレが少ないから。配当性向が基準なら、その決算期の利益が減れば配当も理論上は減る。DOEで使われる株主資本という資産は毎年の変動幅が比較的少ない。
紙田さんによると、TOPIX(東証株価指数)採用銘柄のDOEの平均値は3.6%、中央値は2.9%(2025年3月14日現在)とのこと。
「中央値の2.9%を基準にするといいでしょう。高めのDOE目標を設定している銘柄は増配にも期待できます。
企業は利益の一部を配当として支払い、残りを内部留保として貸借対照表の利益剰余金に蓄えたりします。利益剰余金が増えればDOEの分母にあたる株主資本も増えます。
高DOEをもとに配当すると宣言していたとしたら、新たな利益により株主資本(の利益剰余金など)が増えると配当も増えることになります」
紙田さんによる、DOEの実績値が高い安定配当株をスクリーニングした結果を表にまとめた。



































