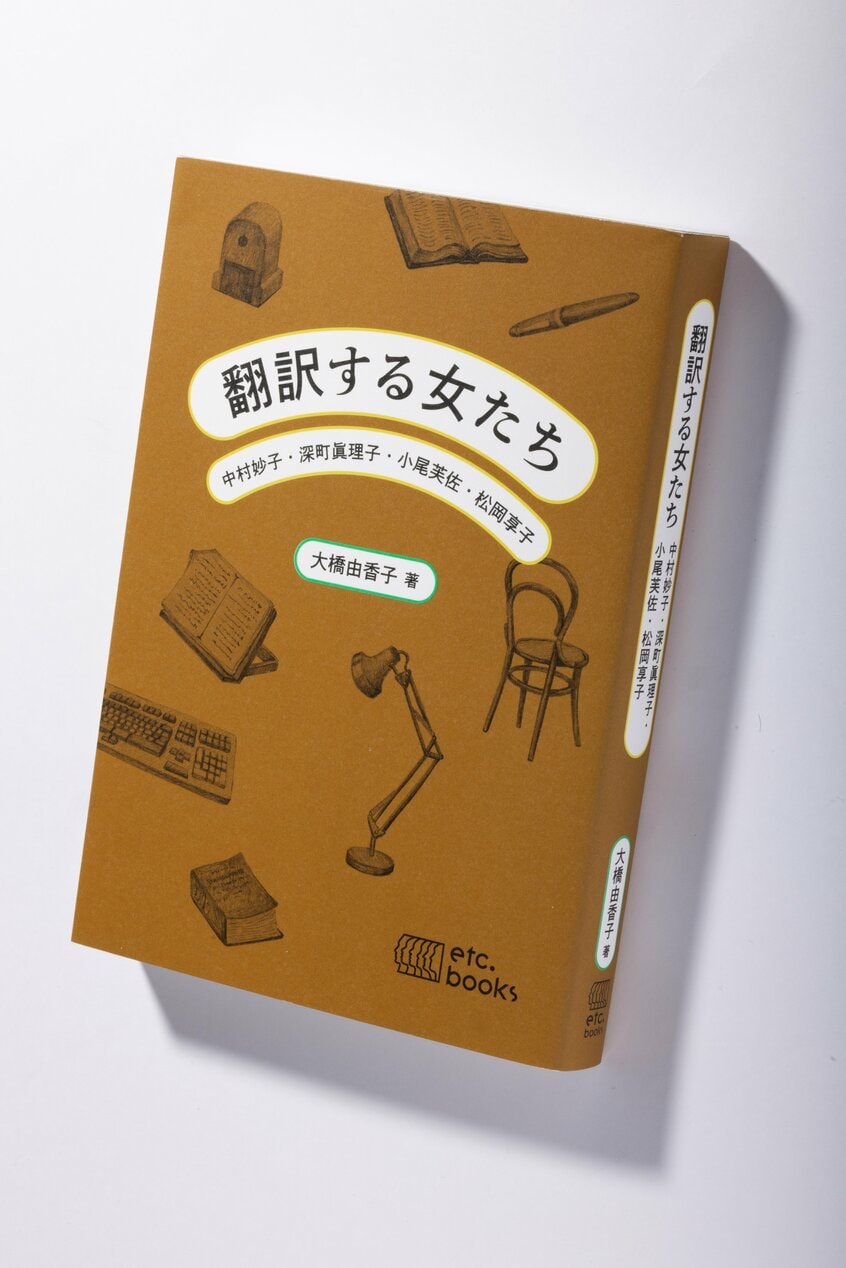
「“不実な美女”たち」というのが、光文社WEBで連載されていた時のタイトルである。「不実な美女」とは、17世紀のフランスやルネサンス期のイタリアから続く、原文と訳文の距離をめぐる翻訳論争で使われてきた例えだ。この例えが長く使われていたことでもわかるように、この業界も男社会だった。語られるエピソードはもちろん一人一人違うのだが、みな現代では想像できないような理不尽を経験し、乗り越えてきている。
「でも、本当に不思議なのは、昔で言う『女傑』みたいな印象とはまったく違う方たちということです。今のフェミニズムの文脈とも少し違っていて、『自分が好きなこと、信じていることを、ただコツコツとやってきただけです』と楚々としておっしゃる。でも、そんなわけないでしょ?と、思わず突っ込みたくなります(笑)」
それにしても、翻訳とは実に厄介なものである。本書の中で深町眞理子さんは「翻訳は、原著者がなにを語っているかを過不足なく読者に伝えるだけでは不十分、それを著者がいかに語っているかまでも伝えられて、はじめて翻訳の名にあたいする」と語っている。それには、計り知れないほどの真摯さが必要だ。
大橋さんは言う、翻訳は「営み」なのだと。
「翻訳は作業であると同時に、生活していく上での一つのスタイルみたいな丁寧な姿勢が求められます。でも、日本語に存在しないものを表現するときには、ちょっとした飛躍や大胆さも必要だったりもします。一文字一文字に注意を払って、背景や意味を何度も調べながら読み込む必要があるので、ある意味で一番深い読書とも言えます。そうやって細部に目を向けることで、理解や愛情がどんどん深まっていく。その姿勢には『営み』という言葉が相応しいと思います」
(ライター・濱野奈美子)
※AERA 2025年5月5日-5月12日合併号
こちらの記事もおすすめ 校正はみんなの「生きる智恵」 情報社会上の人間関係もスムーズに進められる知恵がつく一冊








































