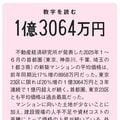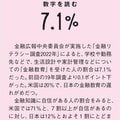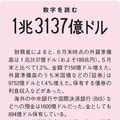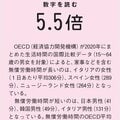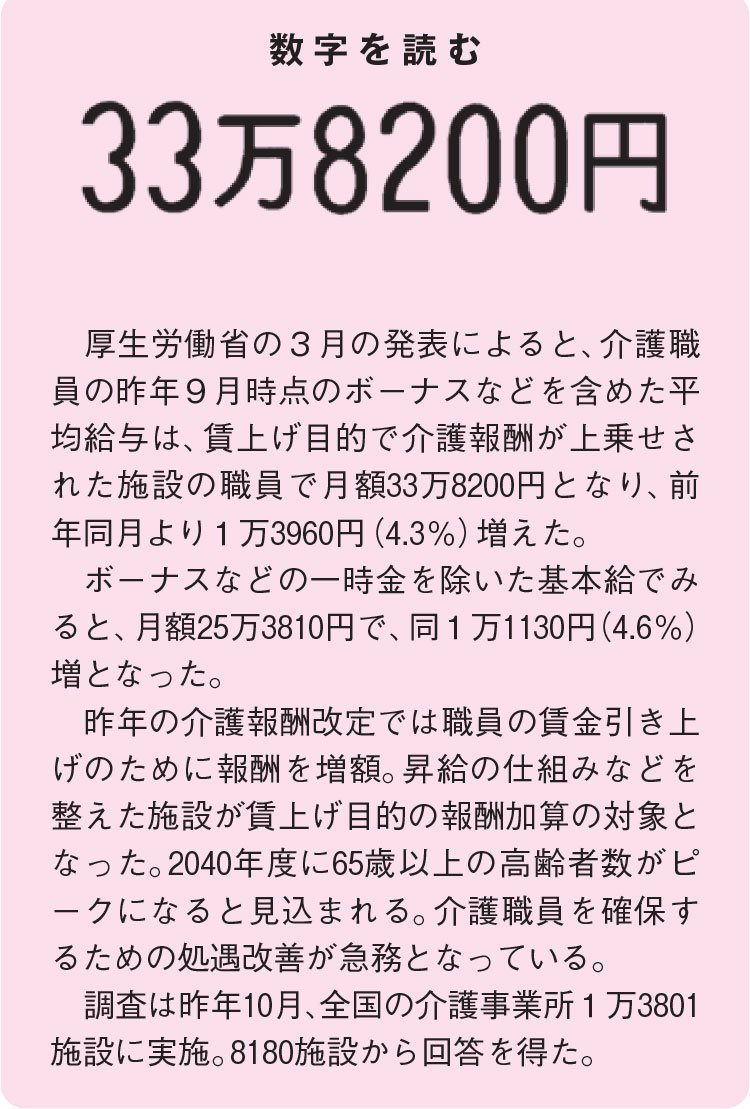
物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年4月14日号より。
* * *
「老人介護」の話に涙するとは、思ってもいなかった。
経済の視点から介護という言葉を聞くと、僕の頭にまず浮かぶのは「負担」の二文字だ。社会保障費の膨張、高齢者と現役世代の負担の押し付け合い、介護施設の経営効率化の必要性──どうしても「コスト」という視点から抜け出せずにいた。
ところが先日、赤坂RED/THEATERで上演されていた劇団兎座の舞台「脳天ハイマー」を観て、その固定観念が根底から揺さぶられた。舞台上で描かれる介護施設の日常は、入居者やその家族、そして介護職員の人生そのものだった。そこでともに暮らす老人たちは、ただ“負担”になる存在ではなく、人生の先輩として教わることも多い。
この作品は鹿児島に実在する介護施設「いろ葉」の取り組みをベースにしている。施設を立ち上げた中迎聡子さんは、高齢者一人ひとりの個性や人生を尊重し、最後まで人間らしく生きられる場をつくりたいという想いでこの施設を開業したという。
いま、介護現場の現実は厳しい。厚生労働省の発表では、2023年の介護職員数は前年から3万人近くも減少したそうだが、高齢者数がピークを迎える2040年までに毎年3万人ずつ職員を増やす必要があるのに、状況はむしろ悪化している。
介護職員の給与は改善されつつあり、昨年9月時点での平均月額は33万8200円で前年より1万3960円(4.3%)増えた。それでもまだ人手不足解消には不十分であり、現場では引き続き負担が大きい状況が続いている。
経済的課題を無視することはできない。人手不足の現実を考えれば効率化が必要なのも当然だろう。だが、効率化という目的が先行してしまうことで、「人間らしい生活」や「尊厳」が後回しになってしまうケースが多く、現場の人たちは歯がゆい思いでいるという話をあちこちで聞く。経済合理性という言葉があるが、本来は人間にとって有益で幸福をもたらすことを意味していたはずだ。