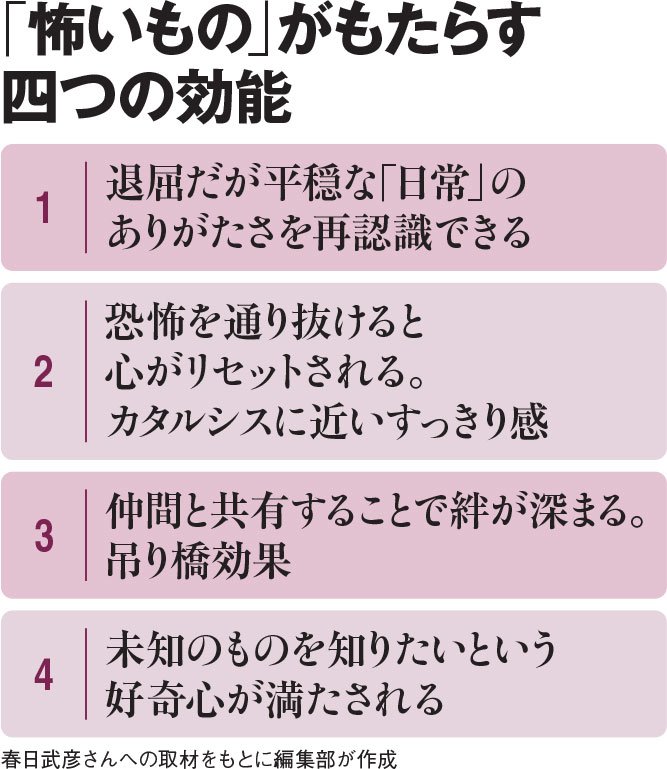
こうした仕掛けも相まって、かつては「子ども」がメインターゲットだったお化け屋敷を大人がエンタメとして楽しむようになった。だが、どれだけ技術が発展しても、変わらない神髄がある。五味さんは言う。
「ただ恐怖を感じさせるだけでは、それは良いお化け屋敷とは言えません。ホラーには、『緊張と緩和』が欠かせません」
お化け屋敷のプロデュースを始めた当初は、お化け屋敷から出てきたお客さんが笑っている姿を見ると「失敗したのではないか」と不安に感じていた。だが、観察を続けるうちに、恐怖による緊張感が緩和する瞬間に「楽しさ」が生まれることに気がついた。
成熟したホラー市場
恐怖と笑いは相反するものに思いがちだが、紙一重のところにあるのかもしれない。それは言葉にも表れている。
「恐怖と笑いを演出する言語表現には共通するものがあります」
と話すのは、中央学院大学商学部教授で日本語学が専門の水藤新子さんだ。移動の合間や退屈な時間にはSNSで怪談を読むなど、「怖いもの好き」の一人。都市伝説と落語は、物語の構成が似ているという。
「語りには巧拙があり、同じ話でも下手に語るとオチが読めてしまう点で、怖い話は笑い話と非常に似ています。最後に怖がらせるか笑わせるか、オチの方向性が異なるだけで、読者の予測をうまく利用しながら、いかに意外な結末を用意して驚かせるかというところも共通します」
怖い話も笑い話も、つきつめると「そんなバカな」とツッコミたくなるものも多い。だが、怖い話はなぜか後を引き、読者の恐怖をかき立てる。
特に近年は、わかりやすい答えのない作品がヒットしている。前出の春日さんは言う。
「恐怖を私なりに定義すると、危機感、不条理感、精神的視野狭窄の三つ。昔は因果応報やたたりを軸とした物語が主流で、話に筋をつけなければ形になりませんでした。ですが、今は『なんとなくイヤな感じがする』といった曖昧なものや不条理なものも受け入れられるようになったと感じています」
1990年代に一世を風靡した『新耳袋』にはじまり、2000年代に生まれた読後感に嫌な気持ちが残るミステリーを指す「イヤミス」など、言い表せない恐怖を求める人がじわじわと増えていった。春日さんは、こうした流れを「ホラーを作る側も受け取る側も成熟した」と見る。
映画、小説、漫画、お化け屋敷……。あの手この手で私たちを恐怖の世界へと誘うホラー作品から目が離せない。(編集部・福井しほ)
※AERA 2025年2月24日号より抜粋




![AERA (アエラ) 2025年 2/24 増大号【表紙:富江(伊藤潤二 描き下ろし・蜷川実花 背景写真)】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CfyXVHznL._SL500_.jpg)





































