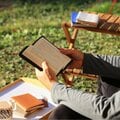日本各地でクマによる人身被害が急増、環境省によると昨年度の被害者は過去最多の219人(死者6人)。今年も8月6日時点の速報値で48人(死者2人)が被害に遭っている。その背景には過疎化や第一次産業の後継者問題などもあるという。AERA 2024年8月26日号より。
* * *
クマが出没する原因の一つは「集落に食べ物があること」。米ぬかを頑丈な場所に保存したり、畑や果樹園を電気柵で囲い、庭木になったものはこまめに除去したりなどの意識が必要だ。
「クマに『来ないでね』と言っても伝わらないですし(笑)、人間の側が賢くなって、『クマが来てもいいことがない環境づくり』をやるしかないんです」(秋田県自然保護課・ツキノワグマ被害対策支援センターの近藤麻実さん(40))
県民全員が「クマとの付き合い方ならちゃんと知ってる。大丈夫」と言えるような、正しい知識を持った県になることを目指したいと、近藤さんは力をこめる。その一方で、「難しさ」も感じている。
クマの捕獲(駆除)への対応をめぐり、秋田県には全国から「パニックになってクマをただ殺している」「何も対策をしていない」など、さまざまな批判が寄せられているのだ。
現在、秋田県では捕獲したクマの「放獣」(山へ返すこと)は一切やっていない。県の「管理計画」にもそう明記してある。
個体数が減っていれば放獣も選択肢として考えるべきところだが、クマに関しては絶滅を心配するレベルからはほど遠く、あえて放獣する必要性も低い、ということも判断の理由だ。
「仮に放獣するならできるだけ集落から離したいのですが、そんな山奥となると国有林。そこへ放すことは不可だと言われて。さまざまな理由で『放せないし、放さない』と決めています」
人の生活圏に出てきた個体は捕獲(駆除)する、という取り組みだ。山奥まで分け入って捕獲しているわけではない。
「『捕獲だけ』に熱心と映っているかもしれませんが、電気柵の設置や放置果樹園の伐採などの対策も進んでいます。地域の努力をきちんと見てほしいです」