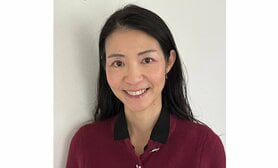5月24日(金)新宿ピカデリー、TOHOシネマズシャンテほか全国公開 配給:ハピネットファントム・スタジオ
© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
ヘスがいつものように子どもを川で遊ばせていると、上流から灰が流れてきた。彼は大急ぎで子どもを家に連れ帰り、浴槽で灰を洗い流した。灰がユダヤ人の遺灰であることはもはや明確である。
このシーンから私の中で塀の向こう側の「音」が増幅された。「無間地獄=ホロコースト」の音。裸にされ、髪を剃られ、シャワーを浴びせられ、ガス室に送られる人々の阿鼻叫喚。もう一つ、ゴーッと轟音が通底していたが、それは焼却音だった。
ヘスは親衛隊上層部からの異動通達に悩む。手塩にかけた収容所を去れという。それを知った妻は半狂乱になって私は子どもたちとこの地に残ると訴える。このまま幸せでいたいと懇願する。そんな姿はどこにでもある中間管理職一家そのものだ。その普通さが虐殺者、略奪者のイメージと同一化し、人を悪魔にする戦争の罪を突き付ける。
このところヘスは胃の調子が悪い。医者の診察を受ける。親衛隊の制服を着て庁舎に上がり、階段で嘔吐までする。天罰だ。彼はここまでだと思ったが、敗戦後、ヘスは戦犯として絞首刑になったと知った。

5月24日(金)新宿ピカデリー、TOHOシネマズシャンテほか全国公開 配給:ハピネットファントム・スタジオ
© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
映画ラストに博物館を掃除する職員の姿が映し出された。彼らの向こうには膨大な髪の毛とメガネ。展示されていること自体が戦争は今も続いているとこの作品は訴える。
この映画を観終わり、ホームで電車を待っていると貨物列車が目の前を通過した。80年前、長々としたこのような列車で人々が「積み荷」として運ばれたのだと思い、時の揺らぎに眩暈がした。
(文・延江 浩)
※AERAオンライン限定記事