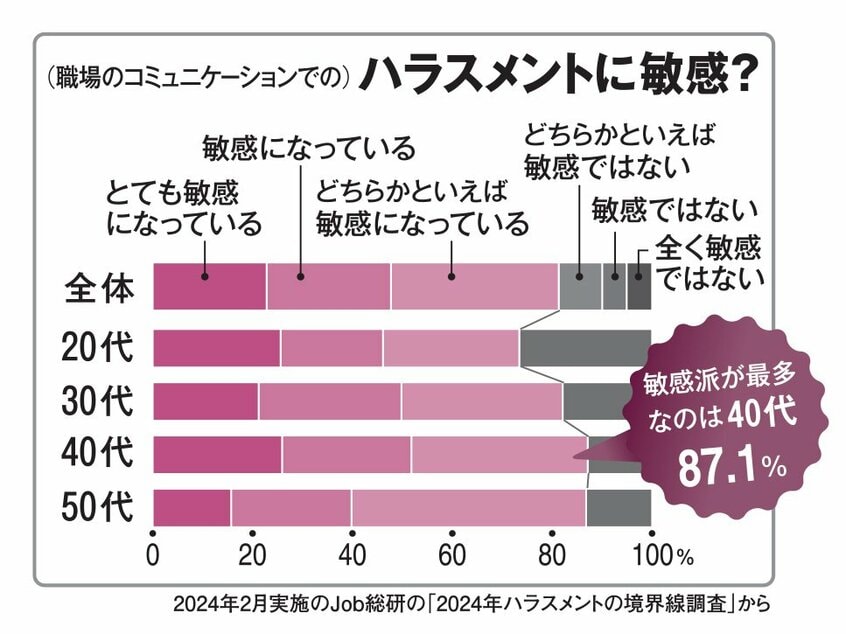
つまり、「回避型上司」のまん延は企業経営に深刻な影響を及ぼすだけでなく、ハラスメント対策にも本末転倒の結果を及ぼしているのだ。その原因は明白だと小林さんは言う。
「同じ職場で働いている以上、何かしらの感情の起伏やトラブルは必ず起きますよね。普段から信頼関係が築けていないと、ちょっとした小石につまずくように、何かが起きた時に過大評価されて『大事』になりやすい、潜在的なリスクを抱え続けることになるわけです」
いま向き合うべきは「ハラスメントを回避しながら、いかに部下を成長させるか」という課題だ。これが両立できている上司に共通する特性は「傾聴行動」の高さだという。部下の話にしっかり耳を傾け、フィードバックできている上司は部下にとっても距離感が近く、職場の心理的安全性につながり、成長実感が増し、ハラスメントも起きにくい。
「つまり、部下がすすんで自己開示できる、腹を割って話せるような聞き方がすごく大事だということ。これは多くの上司が苦手とするスキルです」(小林さん)
傾聴とは「話を聞けばいい」というわけではない。部下がすすんで自己開示できるよう、ジャッジしない、話をさえぎらない、すぐにアドバイスしようとしない、といった「聞き方」のテクニックと同時に、上司がまず自分の悩みや考えについて率直に腹を割って話すアプローチも求められる。ただ、信頼関係はそれだけでは深まらない。
「問われているのは、目の前の部下にあなたはどれくらい興味がありますか、ということです。相手に対する好奇心がベースにないのに傾聴テクニックだけ身につけるのは表面的で上滑りするだけです」(同)




































