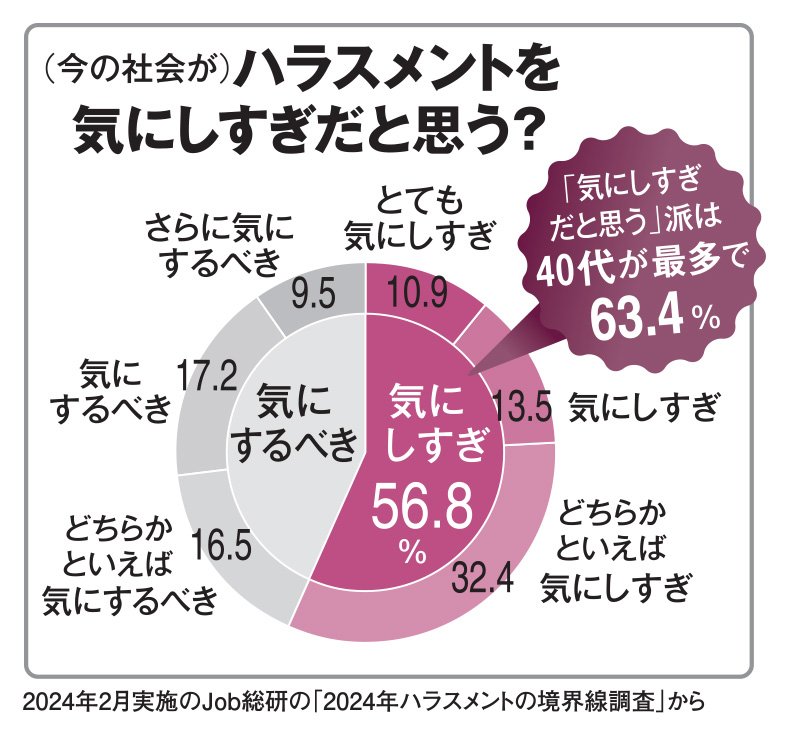
自分の本音に不感症に
上司と部下では見えている世界が違うことにも留意する必要がある。上司は自分も周囲も本音で話せていると思いがちで、部下は自分も周囲も本音で話せていないと感じていることが多いからだ。パーソル総合研究所の「職場の対話に関する定量調査」では、上司側に部下の1.5倍の過剰認識があるという。興味深いのは、本音のコミュニケーションがない職場で働く人は、「自分の本音」に対する関心も低い傾向があることだ。
「ビジネスライクな表面上の会話になれ親しんでいると、自分が本音でどう感じているのか、それをどう表現すればいいのかが分からなくなるんです。そればかりか、そもそも自分の本音が何かなんて大事な問題じゃないと思うようになる。つまり、本音に対して不感症になってしまうのです」(同)
とはいえ、組織のマネジメントは傾聴だけでは済まない。どこまで聞いた時点で、アドバイスや指示に切り替えればいいのか。上司には部下の成熟度や意欲に合わせて、重点を「支援」に置くのか、「指示」に置くのか個別に判断していく能力が求められる。
このように課題を洗い出すと「上司次第」のように聞こえるが、じつはその思い込みがハラスメントの沼から抜け出せない要因につながっている。ハラスメントの原因が職場の信頼関係やコミュニケーション不足によるものである以上、上司だけの問題ではないからだ。小林さんは言う。
「対話や傾聴のスキルは、上司だけが身に付ければいいというわけではありません。根本的には、リーダーシップによって全てを解決しようとする発想を変え、チームのメンバーが主体的・自律的に行動するフォロワーシップ型組織への転換が必要です」
(編集部・渡辺豪)
※AERA 2024年5月13日号より抜粋







































