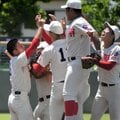介護体験記『いつかまた、ここで暮らせたら』(朝日新聞出版)を出版した翌月、90歳の父が亡くなった。施設で暮らし、入院中だった父を大好きだった家に連れて帰って在宅で看取った10日間の記録を、体験記をつづった大崎百紀がレポートする。AERA 2024年4月15日号より。
* * *
実父の在宅看取りを始めて5日目だった。蒸しタオルで父の顔を拭いていると、父がいきなりこう聞いてきた。
「逝っても、いいか」
不意打ちの言葉に泣きそうになったが、冷静に「逝きたいの?」と返す。すると、
「逝きたい。すごく逝きたい」
父が寂しそうにそう答えた。
その4日後の夜、酸素飽和度は60%まで下がった。
「家のことは心配しないで。ママのことも心配しないで」「聞こえてるよね?」
私の声に父はしっかり頷いた。
その後、意識が低下し、確かなコミュニケーションはこれが最後になった。
翌日の朝6時、ほとんど意識のない父に、私はこう伝えた。
「私のことを心配してとどまってくれてありがとう。もう、逝っていいよ。さようなら」
その17時間後、父は逝った。心拍数120以上の頻脈の状態が半日以上も続き、最後の力を振り絞り、90年も動かしてきた心臓を使いきった。指は少しむくんでいたが、手は最後までほかほかしてとても温かかった。
死んだ日と命日が違う
心停止に至るまでの数十分の経過は消える線香花火のようだった。指につけたパルスオキシメーターの数値が70、60、50と下がり続けるのを夫と二人、ただ見ていた。測定不能となり、機器から異常通知音とともに「エラー」表示が出ると、「あ、逝ったんだな」とわかった。こうやって父は逝った。
事前の指示通り、訪問看護事業所の夜間連絡先に「今逝きました」と電話した。「まだ胸が動いている気がする」と夫が隣で言っていたのをよそに私はサクサクと作業を進めた。父が逝ったのは午後11時20分。できれば医師にはその日中に死亡宣告をしてほしかった。父が最後まで頑張った今日という日を命日として記憶したかった。しかし、間に合わなかった。在宅クリニックの夜勤担当医がやってきたのは1時間後。散大した瞳孔を確認した後、「0時20分です」と言い、死亡診断書に記入した。死因は「誤嚥性肺炎」だった。