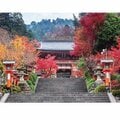紫式部(まひろ)と藤原道長の恋に終止符が打たれ、3月31日放送の大河ドラマ「光る君へ」第13話が描くのは、第12話の4年後。道長の長兄・藤原道隆の娘・定子が一条天皇に入内する。この定子こそ、清少納言が女房として出仕した中宮だ。後に一条天皇は、道長の娘・彰子をも中宮に迎え、紫式部は女房としてこの彰子に仕える。そして、清少納言や紫式部といった女房たちによって物語や随筆、日記といった文学が花開くことになる。
平安文学の担い手となった「女房」とは、どんな存在だったのか。『出来事と文化が同時にわかる 平安時代』(監修 伊藤賀一/編集 かみゆ歴史編集部)から学びたい。
***
正一位から少初位下まで、30階級にも及んだという男性貴族たち同様に、女性たちが出仕した後宮でも、身分は細かく分かれていた。
天皇には複数の妃がおり、正室である皇后・中宮の下に女御(にょうご)、次いで更衣(こうい)があった。後宮の建物は、飛香舎(ひぎょうしゃ/藤壺とも呼ばれた)、淑景舎(しげいしゃ/桐壺とも呼ばれた)などの七舎、弘徽殿(こきでん)、麗景殿(れいけいでん)などの五殿からなり(七舎五殿)、女御や更衣は、「弘徽殿の女御」「桐壺の更衣」など、各自が賜った殿舎の名称で呼ばれることが多かった。
天皇の後宮には多くの女官が働いていた。女官の身分は上臈(じょうろう)、中臈(ちゅうろう)、下臈(げろう)に分けられる。
上臈は中納言(ちゅうなごん)以上の上級貴族出身の女性で、中宮・皇后の食事の給仕や髪の支度などが仕事であった。禁色(きんじき)である赤と青の衣の着用が許されていた。中臈は女童(めのわらわ/小間使いの少女)や下臈の監督、雑用などを務める係で、四・五位の中級貴族出身者が多く、紫式部や清少納言もこのランク。下臈は上級貴族に使える家司や寺社の娘などである。
上・中・下臈の女官たちは、房という部屋を与えられたことから女房と呼ばれた。女房の役割は后の身辺に侍る仕事だけではなく、後宮を運営する事務や儀式への奉仕などの仕事もあり、後宮十二司という12の役所に分けられていた。