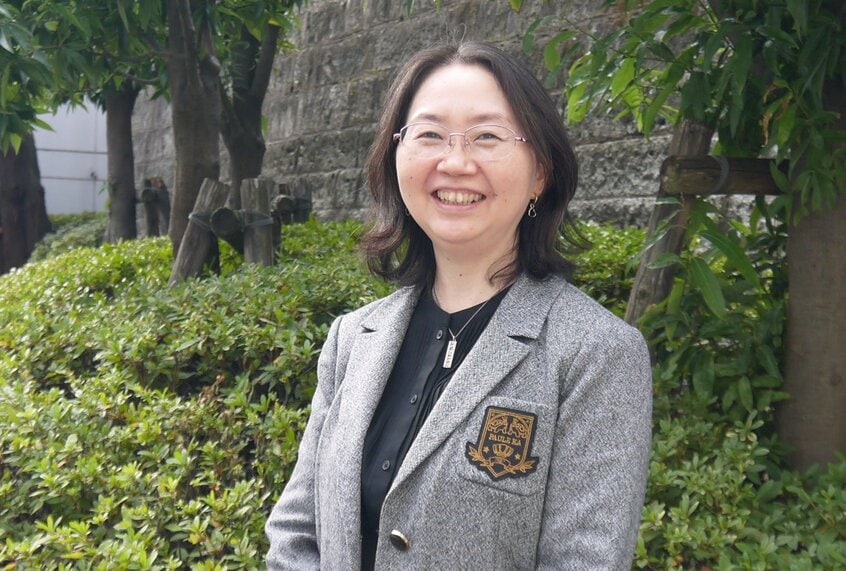
男と女は病気になったときに違いがはっきり出ることがあるので、薬は男女の差を理解したうえで処方する必要がある――この考え方を「性差薬学」として日本に広めているのが、静岡県立大学教授の黒川洵子さんだ。
6年間滞在した米国で不整脈にかかわる心臓の分子機構を研究し、それが評価されて東京医科歯科大学の助手になった。そこで長男を出産、大学の女性研究者支援室の活動に受動的に参加するなかで「女性の健康を守る医療を支える基礎研究が足りていない」という課題に気づく。そこから「性差薬学」という新しい分野への挑戦が始まった。(聞き手・構成/科学ジャーナリスト・高橋真理子)
性差は基礎研究でも注目
――「性差薬学」への注目が高まっているそうですね。
ええ、新薬が市場に出てから撤退するケースについて理由を調べたら、8割が「女性での有害事象の多さ」だったことが大きなきっかけになりました。
新薬の開発には長い年月と多大なマンパワーがかかり、撤退は開発した会社の損害にとどまらず、基礎研究を重ねた科学者や開発を支援した公的機関、そして何より、新しい薬を待ちかねていた患者にとって大きな損失です。思いがけない有害作用を受けてしまった女性たちにも申し訳ないことで、それで開発段階から性差に注目すべきだという考えが広まってきました。さらに、もう一つの背景として個別化医療が注目されてきたことがあります。
――個別化医療というのは、患者一人一人の体質や病態にあった治療法のことですね。昔はオーダーメイド医療とかテーラーメイド医療とも呼ばれていた。政府も大きな予算をつけて推進してきました。
まず行われたのは、患者や健康な人の遺伝子を調べて、その個人差を医療や予防につなげようという取り組みです。ところが、個人差はたくさんあって、それを調べて病気の診断や予防が前より良くなるかっていうと、劇的には良くならなかった。どうしてか。個人差はお互いに関係していないものがたくさんあって、そういう情報をいくら合わせてもばらつきが増えてしまうんですよ。
そこで、男女で真っ二つに分けて解析すると、性別によるばらつきを減らせて、意味のある情報をとりだしやすくなるのではないか、そして、予測率の高い個別化医療が可能になるのではないか、と考えられ始めたんですね。
――なるほど。
生殖器以外の臓器について性差を考慮する研究が欧米で本格的に始まったのは1980年代後半です。日本では、1990年代に天野恵子先生が性差医学を紹介され、臨床の現場で「女性外来」をつくるなどの取り組みがなされるようになったんですが、基礎研究の領域では変化があまり起こらなかった。
それが2015年ぐらいから、ようやく基礎研究でも性別を考慮する動きが広まってきて、最近は性差を論じた基礎的な医学論文もたくさん出ています。
――2015年というと、黒川さんが静岡県立大の教授になるころですね。





































