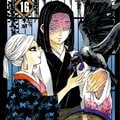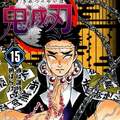■自問自答を繰り返して
技術は確かなのだが、広告やメディアの場で写真を撮り生きることに馴染めず苦労した。40代になり、行き詰まり挫折を自覚していた頃、秋葉原無差別殺傷事件(2008年)が起こる。
「あの事件が起きて人として社会とつながることは、本当に重要なんだとあらためて思ったんです。自分が何をすれば社会とつながることができるのかをすごく考えて。やがて若い人たちに声を掛け、ポートレートを撮っていくことにしました。タイトルは『鏡』。カメラマンとしての挫折を経たら、いい写真でなくても、引きつった顔をされてもいいじゃないかと。それこそ少年少女らの瞳に映る自分です。これがなかったら、その後、サハリンに向き合うことができなかったと思います」
かつてアフリカで心酔したのは人間のすさまじい存在感や野性だった。
「彼らが大地に立っていること。それだけで圧倒されていましたね。彼らがとても大切にしている素朴な闘いの儀式にもとても興味がありました。いま自分が撮っておかなければ、そんな暮らしも失われてしまうのではないか。それであれば自分の人生の時間を注ぎ込めばいいと、若い自分は勝手に思い込んでいましたね」
その後、東京の夜の街に蠢く人びとを追いかけたこともある。強烈な個性を探し求めていた。
「エキゾチックなもの、見たことがない人には、とくに若い頃には惹かれるし、でも本当に興味があるのかと自問自答すれば、至ってノーマルな自分がいて、撮り続けていても結局誰かの真似事になる。僕が向きあうべき人たちは他にいると考えるようになったんです」
自分らしい写真への強い自覚と、大きなテーマが交わり、やがて2010年再びサハリンへ。以後20年まで丹念に撮影を重ねていった。
「10年越しのまなざしは、そこに生きた人間の『消息』と私たちのそれを『国境』を越えてしっかりつなげていくものになっている」(大西みつぐ氏・選評から抜粋)
やがて自分の母親の世代とも近しい女性たちを深く見つめるようになっていた。「どうして今でも日本の言葉を話すのですか?」。その向こうに横たわる人生の重さ、民族や国境の複雑極まりない相克に裸の眼で近づいていった。