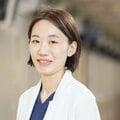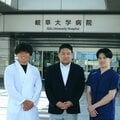耳鼻咽喉科の診療領域には聴覚以外にも非常に幅広い領域が含まれる。頭頸部がん、音声障害、嚥下障害のほか、睡眠時無呼吸症候群やアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎も治療領域だ。
「睡眠時無呼吸症候群になると睡眠の質が悪くなり、アレルギー性鼻炎でも、鼻が詰まると勉強や仕事に集中できなくなる。これらが治療できれば、仕事や勉強もはかどるようになる。耳鼻咽喉科医が患者さんの人生の価値に大きく寄与できる部分です」
中学時代は、次のテストの出題範囲など、教師の言葉がよく聞き取れなかったとき、それを友達に教えてもらうかわりに、友達に勉強を教えていた。もちつもたれつの関係に心地よさを覚え、将来も人を助ける職業に就きたいと、漠然と教師になろうと思っていた。医師を目指そうと思ったのは中3のとき。体育の走り高跳びで転倒、右ひじを骨折した。病院で手術を受け入院。退院時、世話になった主治医の先生と看護師さんに「退院おめでとう」と言われたときだった。「医師になりたい」という得も言われぬ気持ちが湧いた。もともと勉強は苦ではなかった。医学部に現役合格し、医師の道を歩み始めた。
デフバレー日本代表として知名度向上にも寄与
狩野医師には「デフリンピック・バレーボール男子日本代表キャプテン」というもう一つの顔もある。デフリンピックとは、4年に1度開催される耳の不自由なアスリートの国際競技大会だ。
中・高・大学とバレー部に所属し、ずっと健聴者と一緒にプレーしてきた。高校ではレギュラーとして活躍。デフバレーを知ったのは大学3年生のとき。知人からデフバレー日本代表チームへの参加を打診されたのがきっかけだ。
デフバレーも健聴者のバレーとルールもネットの高さも全く同じ。出場条件は両耳ともに55dB以上の難聴者であること。試合中には補聴器や人工内耳を外すのがルールだ。
「難聴者には対話に手話を使う人、口話(こうわ)を使う人、筆談の人もいる。練習での話し合いでも、メンバーと意思疎通がすんなりできない。最初はそこが大変でした。私は普段、口話でやりとりしていますが、手話も学んでいたのでそれが役立だちました」
普段はそれぞれ仕事を持ち、全国にちらばるメンバーとの練習は月1回程度。そうした状況でもチームは健闘し、17年トルコ大会は7位、21年ブラジル大会(22年開催)8位入賞。次は25年の日本初開催となる東京大会を目指す。
悩ましいのは、デフリンピックはオリンピックやパラリンピックに比べ、認知度が低いことだ。「東京大会を契機にデフリンピックの認知度向上、補聴器や人工内耳も啓発していきたい」と意気込む。