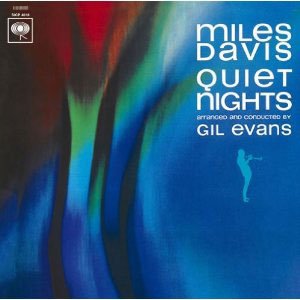
本日5月26日はマイルスの誕生日ですが、今日、ニューヨークでは盛大なセレモニー及びイヴェントが行なわれます。かつてマイルスが住んでいた77丁目の西312番地周辺が「マイルス・デイヴィス・ウェイ(Miles Davis Way)」と命名され、その除幕式(と言っていいのでしょうが)が執り行なわれるのです。いやーこれはめでだい!
今年の夏休みにニューヨークに行かれる予定の方は、ぜひ訪ねてください。55丁目あたりからセントラル・パークを右に見ながらトボトボと時間をかけて歩いていくと、やがてジョン・レノンが住んでいたダコタ・ハウスやその他有名な観光スポットを自動的に訪れることになります。それではパート2の今回は、現在もなお賛否両論を呼んでいる『クワイエット・ナイト』です。なぜ賛否を呼んでいるのでしょう?
このアルバムほど数奇な運命を辿ったものもないだろう。そもそも『クワイエット・ナイト』というアルバムは、本来であれば「存在してはいけないはず」のものだった。1962年の前半、マイルスはベストのメンバーを確保することができず、さらには体調の不良もあり、ほとんど活動していなかった。そこでレコード会社が提案したボサ・ノヴァの録音に応じる。当時ボサ・ノヴァは大きなブームを呼んでいた。ただしマイルスは交換条件としてギル・エヴァンスとの共演を挙げ、シングル盤のみの発売ということで同意する。
7月27日、マイルスとギルはシングル用のセッションを行ない、アントニオ・カルロス・ジョビン作《コルコヴァード》及び《アオス・ペス・ダ・クルーズ》を吹き込む。それらは2枚のシングルとして発売されたがヒットには至らず、ここでマイルスとギルのボサ・ノヴァ企画は予定どおり終わる。とはいえ創造に火がついた2人はその後も変則的な顔ぶれによるセッションを断続的に行ない、8月には新しいシングル用として、ボブ・ドロー(ヴォーカル)を主役に立てた《デヴィル・メイ・ケア》を吹き込む(これはボサ・ノヴァ企画とは無関係)。また11月には、可能性を探るという意味合いから、発表を前提としない上で《ソングNo.2》や《ワンス・アポン・ア・サマータイム》を録音し、同時にセッションを打ち切る。
この時点で『クワイエット・ナイト』というアルバムは存在していなかった。しかし新作が途切れることに危機感を抱いたレコード会社は、前述した複数のセッションと翌63年4月の『セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン』で吹き込まれた演奏(《サマー・ナイト》。サックス奏者ジョージ・コールマンは不参加)を抱き合わせ、『クワイエット・ナイト』と題したアルバムを発売する。それはマイルスもギルも満足していなかった、わずかの本番(マスター・テイク)とリハーサルの音源を寄せ集めた企画盤だった。『クワイエット・ナイト』は64年3月、アメリカで発売された。そして次のような伝説が生まれる。「腹を立てたマイルスは、テオ・マセロ(プロデューサー)と2年半にわたって口をきかなかった」。次にマイルスとテオ・マセロがスタジオで本格的な共同作業を再開するのは、『クワイエット・ナイト』発売から「2年7か月後」の『マイルス・スマイルズ』となる。伝説は真実だった(のかもしれない)。
ボーナス・トラックについて触れておこう。マイルスとギル・エヴァンスは63年10月9・10日、ハリウッドのスタジオで、ピーター・バーンズ作の舞台劇『ザ・タイム・オブ・ザ・バラクーダ』の主題曲の録音を行なった。プロデューサーはアーヴィング・タウンゼンド。9日がリハーサル、10日が本番となった。同曲はマイルスとギルが共作し、マイルスのグループからハービー・ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスが、ギルが指揮するオーケストラのメンバーとして参加した。最新版『クワイエット・ナイト+1』には、このセッションから《ザ・タイム・オブ・ザ・バラクーダ》のテイク20が収録されている。なお舞台劇は10月21日サンフランシスコ公演から11月23日ロサンゼルス公演まで主に西海岸で巡演され、マイルスとギルが吹き込んだ演奏はテープで流された。
最初はシングル盤のつもりだったものが、気がついたときにはアルバム(LP)になっていた。それはマイルスやギルでなくても立腹するだろう。しかしこの『クワイエット・ナイト』というアルバムは、そのような数奇な運命を辿らなければ生まれようのない手触りをそなえている。そして存在感が希薄なことが逆に存在感を生むという奇妙な結末を呼び込み、そう、この音楽は何かに導かれているような「不思議な手応え」を感じさせる。現在では「アンビエントな響き」の原点のようにも思える。マイルスとギル・エヴァンスそしてテオ・マセロを「導いたもの」は、音楽の神か、あるいはボサ・ノヴァのミューズだったのかもしれない。[次回6月16日(月)更新予定]


































