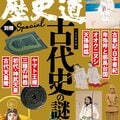小田原北条氏の滅亡後、家康は関東に移封となり、江戸城を築いて本拠とした。駿府城は秀吉家臣の中村一氏に与えられた。その後、関ヶ原の戦いを経て家康は将軍となり、駿府城には徳川家臣が入る。やがて将軍を辞して大御所となった家康は、慶長十二年(1607)に駿府城に移り隠居城とした。この時、城を拡張して新たな天守や御殿を築くも火災で焼失。家康はすぐに、焼失した天守や本丸御殿の再建に乗り出す。天守が完成したのは慶長十五年のことだった。つまり、家康が築いた駿府城の天守は、天正期と慶長期に二つ、計三つ存在したことになる。小和田さんはこう語る。
「家康が2度目に築いた慶長期の天守も、江戸時代前期には焼失してしまい、再建されることはありませんでした。明治になると駿府城は廃城となり、陸軍の歩兵連隊が置かれることになったため、天守が建っていた土台である天守台も壊されて、その土砂で本丸の堀を埋め立ててしまったんです」
静岡市は、平成二十八年(2016)から令和二年(2020)まで、駿府城天守台石垣の発掘調査を行った。まず、家康が築いた慶長期の天守台が見つかった。一辺が60mを超える巨大な天守台で、発掘当初から、日本最大規模の天守台であると発表され、話題となった。
※インタビュー構成/安田清人(三猿舎)