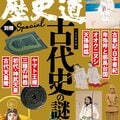小和田さんらの保存運動が実り、美術館は別の場所に建てられることになり、遺跡は地中に埋め戻されて保存されることになった。「静岡の変」とも呼ばれたこの保存運動をきっかけに、全国各地で城跡などの保存運動が起きたという。
「若き日の家康が暮らした駿府は、今川氏という大大名のお膝元で、まさに小京都と呼ぶにふさわしい都市でした。もし機会があれば、今川館の遺構を改めて発掘して、その全貌を明らかにできれば、と思っているんです」
かつて城跡は、官公庁などの公共施設に活用されていた。しかし近年、歴史に触れることができる史跡公園として活用しようという機運が高まっている。
地中から姿を現した
天下人家康の城の威容
駿府城二ノ丸の東御門を入り二ノ丸を抜けると、間もなく本丸に入る。本丸の一番奥に当たる北西部の隅に、かつて徳川家康が築いた巨大な天守がそびえていた。三河国の岡崎城を本拠としていた家康は、やがて今川家の領国であった遠江国に進出し、元亀元年(1570)に浜松城を築城して移った。武田信玄と同盟を組んで今川氏真を東西から挟み撃ちにした家康は、やがて今川氏の本国である駿河国をも手中に収める。そして武田氏滅亡後、甲斐国信濃国をも併呑して五カ国を領有する大大名へと成長する。
しかし、織田信長の事実上の後継者となった羽柴(豊臣)秀吉と対立し、天正十二年(1584)に小牧・長久手の戦いへと突入。明確な勝敗はつかず講和を結んだ。家康は、これを機に駿府城を築き、新たな居城とすることになる。
なぜ家康は駿府に居城を移したのか。小和田さんはこう語る。
「新たな領土である甲斐や信濃を統治するのに、浜松よりも駿府の方が距離も近く、有利だったからでしょう。また、秀吉と講和を結んだとはいえ、家康が秀吉に完全に臣従するのは駿府築城(天正十三年)の翌年です。国を守るために秀吉政権から距離をとりたいというのも、理由の一つだったと思います」