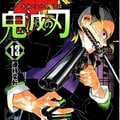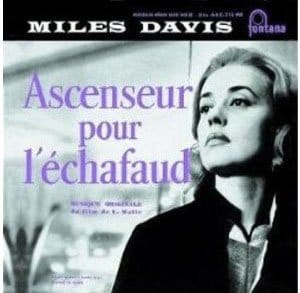

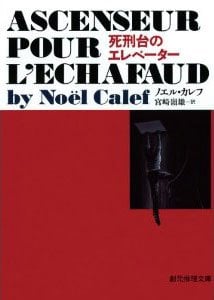
このコーナーも5回目になった。どうもマイルス・ファンには不評らしい。先日も「もう『マイルスを聴け!』はやめたんですか」という、軽い失望と憤怒が入り混じった声が届いた。「いや、やめたわけではなく、『マイルス・アット・フィルモア』の《木曜マイルス》の完全版が出たら、まとめて紹介します」と答えたのだが、どうも相手は納得していないらしい。
補足すれば、現在の「ミュージック・ストリート」は、前身にあたる「ジャズ・ストリート」のリニューアル・ヴァージョンで、ぼくはその「ジャズ・ストリート」でかなり長い間、拙著『マイルスを聴け!』を補完する意味も含め、同名の連載をもっていた(週1回更新。現在はこの「ミュージック・ストリート」のアーカイヴとして公開)。それが「ミュージック・ストリート」になったとたん、すっかり様相が一変した。そのことに対して、どうやら「あんた、冷たいんじゃないの」という声が一部で上がっているらしい。
それはそれとして、過日、久しぶりに映画『死刑台のエレベーター』を観た。そこで今回は、マイルス・デイヴィスが音楽を担当したこの映画のサウンドトラック盤に関する「誤解」について、個人的な思い出とともにまとめてみたいと思う。
ぼくがジャズを聴くようになったのは、60年代の終わり、たしか1968年前後のことだった。これをジャズの動きと時系列で対比させれば、マイルスの『カインド・オブ・ブルー』が録音・発表されてから、まだ10年も経っていなかったことになる。そのときはそういうふうには考えられなかったが、いまでは「そうだったのか」と、じつにさまざまなことを思い、感慨にふける。
当然のことながら、いわゆるジャズ初心者としての悩みや苦労を味わったが、そのなかに「定説と合わない」ということがあった。つまりジャズの雑誌や本では「定説」あるいは「常識」として書かれていることが、どうも自分の耳にはそのように聞こえない。だから、その定説というものを信じることができず、しかし「定説」というくらいなのだから、おかしいのは自分のほうだと思い、ついつい自分のジャズ体験の未熟さを呪ってしまう。とまあ、そのようなことがしばしばあった。
ところが人生とはよくしたもので、同じように考えている人間、いわゆるジャズ仲間が知らず知らずのうちに集まってくる。そうすると勇気百倍、おかしいのは自分(たち)ではなく、定説やそれを書いたり吹聴したりしているほうではないかと考えるようになる。
そのひとつに、マイルスの『死刑台のエレベーター』に関する一件があった。定説では、そのサウンドトラック盤は、マイルスが映画の映像を観ながら即興で吹き込んだといわれていた。だからすごいのだと。
ぼくは、ジャズ初心者ながら、これに悩んだ。どう聴いても、何度聴いても、その音楽は事前に作曲されているようにしか聞こえない。そういう疑惑を抱かせるほど、この即興能力は高いということなのだろうか。そんなことはないだろう。
ある曲では、ベース・ソロしか出てこないが、これなんか、どう解釈しても完全な即興とはいえない。マイルスを中心にしたグループの演奏も入っているが、どう聴いても、きちんとリハーサルが行なわれ、一糸乱れぬグループ表現として完成している。
こういう「聴けばわかる」ような「かんちがい」が、ジャズの世界では「定説」となっていることが多いということに、その後しばらくして気づく。現在では、映画を監督したルイ・マルや、マイルスをフランスに招聘したマルセル・ロマノーの証言によって、マイルスが宿泊していたホテルの一室にピアノが運び込まれ、マイルスが作曲に没頭していたことが明らかになっている。つまりマイルスは、一度か二度、試写というかたちで映画を観た上で作曲に入り、スタジオでそれらを何度か演奏し、ルイ・マルがテイクを選び、実際の映画に挿入した。
しかしながら、この年季の入った「定説」は、ユーチューブによって、ますます強固に、まちがった方向に塗り固められつつある。そこにはマイルスが映画の映像を観ながらトランペットを吹いてる映像がアップされ、よって「定説」を裏付けるものとなっているかのように思えるが、その映像は、『死刑台のエレベーター』が録音された翌年、たまたまフランスに滞在していたマイルスに頼み込んで、テレビ番組で流す宣伝用として撮影された、いわば「やらせ」の映像にすぎない。マイルス一人だけが、しかも正装をして「口パク」でトランペットを吹いている映像を観て、不思議と思わず、「ほーら、やっぱり定説はまちがっていなかった」と喜ぶ人がいるところに、この種の「定説」の吸引力が潜んでいるのだろう。要は「定説は真実より強し」ということなのかもしれない。
この一件は、耳や感性の優劣のように聞こえる危険性があるが、それこそ「聴けばわかる」といった類のことであり、昨今は、この「聴けばわかる」ことさえすっ飛ばされているようにみえる。すっ飛ばし、感想めいたことをツイッターで流し、それでおしまい。その音楽が二度三度と聴かれることはあるのだろうか。そういった風潮を少々淋しく、残念に思う。[次回5月27日(月)更新予定]