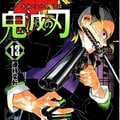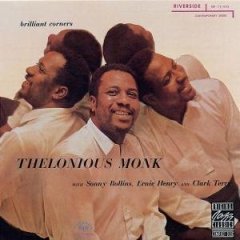
●ジャズの枠を越えている、一筋縄ではいかない音楽
ジャズをあまりよく知らない人たちにとって、モンクはいかにも“ジャズっぽい”ミュージシャンに映るかもしれない。ジャズ=変わった音楽、という、当たらずといえども遠からずなイメージに、彼の音楽はピタリと当てはまる。
一方、ある程度ジャズに親しんだファンは、モンクがジャズの中でも特別のユニークな存在であることを知っている。“モンクス・ミュージック”という言い方があるが、それは暗にモンクの音楽がジャズの枠を超えていることを含意しているようにも思える。
私自身の「モンク体験」を振りかえってみても、彼のことはかなり「初心者」の段階から知っていた。そして、直感的に当時私が親しんでいた60年代アメリカンポップスから、一番離れたところにある音楽であると感じたものだった。
その後、一応「ジャズ史」みたいなものも齧ってみると、モダン・ジャズピアノの開祖バド・パウエルにいろいろ教えたなどという記述にぶつかる。にもかかわらず、現実のバップ・ピアニストたちの演奏からはモンクの影響を聴き取ることは難しい。つまりは、一筋縄ではいかないミュージシャンなのだ。
●ちょっとへんなのに、惹かれてしまう
モンクの演奏を聴いた人が誰でも思うのは、「ちょっとヘン」という感覚だろう。メロディが変わっている、リズムもちょっと異様。それにもかかわらず、彼の音楽には人を惹き付ける魅力がある。その理由を探ってみよう。
まず、彼の作る曲はどれもユニークだが、一貫性がある。ためしに何曲か彼のオリジナル聴いた後で、彼の未知の曲目を聴いてみれば「あ、これもモンクじゃない」とすぐ気が付くはずだ。つまりは、他人にはうかがい知れないが、モンクの創る曲には彼の一貫した美意識というかロジックというか、とにかく一本スジが通っているのだ。
それは演奏にもいえて、パウエル流のバップ・ピアノとはかなり趣が異なっているけれど、決してその場の思いつきといったものではない。有名な彼のオリジナル《ラウンド・ミッドナイト》の録音風景を記録した《ラウンド・ミッドナイト・イン・プログレス》というトラックを聴くと、モンクは自作曲をどのように展開するかについて実にさまざまなアプローチを試みている。変わっているように聴こえて、モンクは自分の出すサウンドの響きをトコトン考え抜いているのだ。だから、彼の演奏は異様ではあるけれど、破綻することはない。
●バンドリーダーとしての凄さ
ピアニストには、自分の演奏だけで聴衆をノックアウトしてしまうパウエルのようなタイプもいるが、モンクはバンドリーダーとして自作曲を取り上げることによって、自らの世界を提示するミュージシャンであると言えるだろう。
興味深いのは、それにもかかわらずモンクのバンドではどのサイドマンも自由に個性を発揮させているところだ。ちょっと考えると、モンクのようなアクの強いリーダーのもとでは演奏に枠がはめられるのではないかと想像しがちだが、そうはなっていないところがモンクの凄さだ。
彼の代表作である『ブリリアント・コーナーズ』では、サイドのソニー・ロリンズもアーニー・ヘンリーも見事にモンクの世界を描きつつ、彼ら自身も輝いている。モンクの作る曲は不思議な力があって、その中でさまざまなタイプのミュージシャンが自在に遊べるのだ。
そのことはモンクの死後作られたハル・ウィルナーによる追悼盤『セロニアス・モンクに捧ぐ』(A & M)を聴くと良くわかる。モンクゆかりのジャズマンからロック・ミュージシャンに至る実に多彩な演奏家がモンクの曲目を取り上げつつ、各自の音楽を表現している。“モンクス・ミュージック”がジャズを超えていると言われるのは、彼の音楽がこうした広がりを持っているからなのだ。
【収録曲一覧】
『ブリリアント・コーナーズ』(Riverside)
1. ブリリアント・コーナーズ
2. バルー・ボリヴァー・バルーズ・アー
3. パノニカ 4. アイ・サレンダー,ディア
5. ベムシャ・スウィング
セロニアス・モンク:Thelonious Monk (allmusic.comへリンクします)
→ピアノ奏者/1917年10月10日 - 1982年2月17日