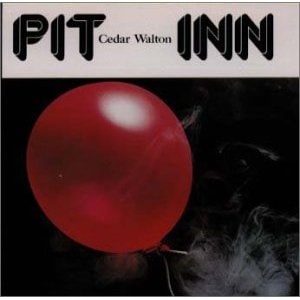
Pit Inn / Cedar Walton (Universal [East Wind])
1974年12月、シダー・ウォルトン(ピアノ)はサム・ジョーンズ(ベース)とビリー・ヒギンズ(ドラムス)を引き連れて来日する。アート・ブレイキー(ドラムス)の率いる「ジャズ・メッセンジャーズ」(1963年1月)、ジャム・セッション(64年11月)、再び「ジャズ・メッセンジャーズ」(73年2月)の一員として訪れた過去3回とはちがって、当時のワーキング・グループだった自身のトリオを率いての来日だった。滞日中に4作の録音に参加する。サム・ジョーンズ名義のウィズ・ストリングス作『セヴン・マインズ』(21日/イースト・ウィンド)、3日連続で新宿「ピット・イン」でライヴ録りされた、笠井紀美子の『キミコ・イズ・ヒア』(22日/CBSソニー)、トリオ単独の本作(23日/イースト・ウィンド)、『渡辺貞夫・アット・ピット・イン』(24日/CBSソニー)だ。いくらウォルトンが主役を張ったとはいえ凡作ならとりあげない。快ライヴでよかった。
当時のウォルトンに対する評価は「中堅の名手」という当たり障りのないものだったと記憶する。上手いことは上手いのだが良い意味での癖がなく地味な印象を与えたようだ。ウォルトンのピアニズムの全貌を捉えたトリオ作がなかったことも一因だろう。今でこそ50作を超えるリーダー作の3割強がトリオ作だが、当初はホーンを入れたカルテット作やクインテット作しかなく、8作目でようやく初のトリオ作となった『ファーム・ルーツ』(1974年4月/ミューズ)はまだ発表されてはいなかった。発表が1年先行した本作こそリアルタイムではウォルトン初のトリオ作になる。それまで代表作といえば初リーダー作『シダー!』(1967年7月/プレスティッジ)くらいしかなかったが、本作はそれに並ぶ快作にちがいないと大いに感心したものだ。ナマで聴いた潜伏期間の村上春樹氏が本作を『意味がなければスイングはない』(文藝春秋/2005年)で絶賛したことでも知られる。
LP時代のA面から。食い付きのいい好曲《スイート・サンデイ》は格好のオープナーになった。快適なサンバのリズムに乗って無限ループにも思える優美なソロをひとしきり、ショパンにサンバを弾かせたらこうなりそうな感じだ。ソロに転ずるとルバート→フォービート→ワルツとつなげて再びサンバに戻り、ヒギンズの退屈させない立派なソロを経てサンバに戻る。組曲というだけあって構成の妙に富んだ快演だ。このオープナーで誰しも快ライヴを確信するだろう。しかし、これは序の口だった。続くミディアム系の《コン・アルマ》はグイグイ突き進むゾクゾクするほどの力演なのだ。ウォルトンは心技体充実、ヒギンズの小ワザが光る。ファスト系の《ウィズアウト・ア・ソング》ではウォルトンが淀みなく歌うこと歌うこと、中盤からのドラムスとの小節交換もヒギンズが練達のワザを繰り出してまったく飽かせることがない。これまた生命感と躍動感に満ちた力演だった。
LP時代のB面に移って、ゆったりしたテンポの《サントリー・ブルース》《ラウンド・ミッドナイト》をツマランといってはいけない。これはこれで格好の箸休めと聴くべし。その通り、あとにこの日一番の力演がくる。ファスト系の《ファンタジー・イン・D》はサイドマンにソロをまわさずウォルトンが7分23秒を一気呵成に弾き抜く渾身の力演だ。クローザーの《ブリーカー・ストリートのテーマ》はミディアムのマイナー・ブルース、心地よいグルーヴに思わず腰が横揺れするなかウォルトンがメンバーを紹介、快ライヴに幕が下りる。これをピアノ・トリオ・ファンだけに楽しませては勿体ない。ウォルトンの代表作に数えて然るべきだ。『シダー!』や『イースタン・リベリオン』(1975年12月/タイムレス)とともにコレクションに加えてほしい。いまのところ入手難だがLPを含めて中古に当たられるといいだろう。その手間は十分に報われる、ピアノ・トリオの名盤だ。
【収録曲一覧】
1. Suite Sunday
2. Con Alma
3. Without A Song
4. Suntory Blues
5. 'Round Midnight
6. Fantasy In "D"
7. Bleecker Street Theme
Cedar Walton (p), Sam Jones (b), Billy Higgins (ds)
Recorded At Pit Inn, Tokyo, December 23, 1974


































