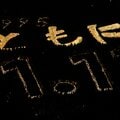長岡駅から南へ向かい、カーブの続く山道を車で30分ほど上がると、棚田が現れる。錦鯉の看板もちらほら。この辺りが旧山古志村(現・長岡市)だ。
秋になると、棚田が黄金色に輝き、まるで桃源郷のよう。一年を通して、全国から写真愛好家が集まるフォトジェニックな山村だ。10年前にあの大惨事があった場所とはとても思えない。
2004年は今年のように雨が多い年だった。7月には大水害が起き、10月までに台風は日本に10個上陸。地盤が緩んでいたところに、直下型地震が襲った。旧山古志村では地滑りでせき止められた芋川が氾濫し、集落が水没。陸の孤島となり、震災2日後には全村避難になった。
新潟県全体では、死者は68人、負傷者は4795人。土砂に巻き込まれ、4日後に奇跡的に救助された皆川優太ちゃん(当時2歳)を覚えている人も多いだろう。
震災の翌年3月に、県は3千億円の県債を発行。10年間で住宅再建や起業支援など約654億円の事業を行ってきた。今、震災の爪痕はほとんどない。
しかし、1カ所だけ当時のままの場所がある。それが水没した木籠(こごも)集落だ。震災遺構として被災した家が数戸残されている。
「家を撤去する話を聞いたとき、残さなくてはと思ったんです。一度なくしたら取り戻せない」
同地区の松井治二さん(74)はそう話す。松井さんが発起人となり、4年後に保存が決定。今では観光客だけでなく、全国から視察も来るという。
「震災前の状態に戻ったかな、と実感できたのは昨年くらい。家や棚池の修復に丸3年かかり、5年間は実質無収入でした」
そう話すのは、丸重養鯉場3代目の田中重良さん(34)。棚池は40枚ほど崩れ、約200匹の鯉が死んだ。生き残りや買い足した鯉を育て、ここまできた。
10年経ち、新たな不安もある。高台移転した“天空の郷”に住む藤井寛之さん(34)は語る。
「今心配なのは集落の維持。少子高齢化が進み、移転後、2世帯減りました。新しい建物があっても、人がいなきゃ……」
ここからがまた、新たなスタートなのだろう。
※週刊朝日 2014年10月31日号