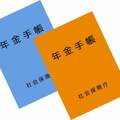今や、介護者の3人に1人が男性の時代。誰にも弱音を吐けず、グチもこぼせず、社会から孤立して介護にだけ向き合っている男性は多い。そんな男性たちが集まって、悩みを打ち明けたり、情報交換したりする会が増えている。
* * *
男性介護者の会は、男性の介護者が増えるに従って、全国に広がっている。男女ともに参加できる介護者の会もあるが、男性だけの会が、最近増えつつある。
「男の人は、見えをはってしまって、グチや悩みを他人に言えない。プライドが邪魔をして、女性に相談しづらいことも多い。だから、男だけで話す場所、聞ける場所が必要なんです。自分だけじゃないと思えることが大事」
そう語るのは、東京都荒川区にある男性介護者の会「オヤジの会」の事務局を担当する神達五月雄さん(52)だ。「オヤジの会」では、奇数月に1回、昼に1時間ほど集まって悩みを打ち明けたり、情報を交換したりする。また偶数月に1回、定例会として講師を招いて勉強会をし、その後に懇親会を開いている。
「懇親会はお酒を飲みながら。ただお酒を飲むだけとなると、気が引けて外出できない男性も多い。勉強会をすることで、自分にも家族にも言い訳ができるんです」(神達さん)
同じく男性介護者の会で、大阪市住吉区にある「ほっこりサロン」でアンケートを取ったところ、7割の男性が介護にストレスを感じていると答えたという。「ほっこりサロン」を支援している、住吉区地域包括支援センターの女性職員が言う。
「男性は女性と違って、井戸端会議ができないので、孤立してしまうんですね。こんなことまで聞いていいのかと思って、聞くことができずに情報不足になる。グチを家族にも話せず、誰かに聞いてもらうこともできない。でも男性同士なら、思いを共有することができる。話をすることでスッキリし、元気が出るようです」
「ほっこりサロン」では、設立3周年記念イベントとして「できる男の生活講座」を開いた。スキンケア講座、食事講座、おそうじ講座、お洗濯講座と、すべて男性の講師を招いての勉強会を企画したところ、各講座とも30人以上が参加するほどの盛況ぶり。特にスキンケア講座では、「どういうときに使ったらいいんですか?」と、妻や母の持っている化粧水や乳液に関して質問が続出。予定していた講義が全部できなかったほどだった。
都内の自宅で、認知症の父を母と交代で介護している齊藤拓さん(51)も、積極的に人とつながるようにしている。
「僕は『クラブ・ウィルビー』の会員になっていて、興味のあるイベントには、顔を出すようにしています。最近は『介護カフェ』も企画されているので、それにも行っているんです」
「クラブ・ウィルビー」とは、プロデューサーで、自身も現在母親の介護をしている残間里江子さんが立ち上げた、イベントやセミナーを通して大人同士でつながることを目的とした会員制の会だ。「介護カフェ」も、「クラブ・ウィルビー」で企画されたもので、介護をしている人だけでなく、関心のある人や、これから介護をするかもしれない人が、男女問わず集まれる。
齊藤さんは食事の用意で時間的拘束もあるし、両親が心配なので遠出はできない。ただ、自宅まで30分程度で帰れる場所でのイベントなら顔を出すようにしている。
「『クラブ・ウィルビー』は僕にとって心強いものです。精神的にも安定しますね」
人に聞いたり、話したりすることを恥ずかしがらずにできるという齊藤さんは、比較的うまくストレスと折り合っているようだった。
※週刊朝日 2014年3月14日号