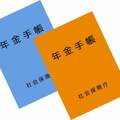「胃ろう」という人工栄養補給によって、寝返りも打てずに、ベッドにじっと横たわったままの高齢者の数は30万人とも40万人とも言われている。この現実に「命を延ばす」ことだけが本当に正しいのか、と疑問を感じた特別養護老人ホーム「芦花ホーム」の石飛幸三(いしとびこうぞう)医師(77)は「平穏死」という新しい考え方を提唱している。その言葉の成り立ちを氏はこのように説明する。
* * *
2009年の夏ごろでしょうか。昔、お世話になった黒田和夫弁護士の事務所に挨拶に立ち寄ったのです。いま携わる芦花ホームの様子を話し、黒田弁護士にこうたずねました。
「医師が、延命治療をしなければ、本当に“不作為の殺人”になるのですか」
そうしたら、私ひとりのために2時間使って不作為の殺人の定義について、講義をしてくれたのです。黒田弁護士は、「尊厳死や安楽死という言葉はあるけど、石飛先生が考えておられるのは、そのどちらともちがいます。肉体的にも精神的にも苦痛がなく穏やかに亡くなるというと、『平穏死』ですかね」
私は思わずこう叫んでいました。「黒田先生。まさにそれです。『平穏死』という言葉をぜひ使わせてください」。
我々に数人の医師や弁護士が加わり「平穏死」を法的に考える勉強会が始まりました。医師が安心して「看取り」医療をできるようになるための道標になればと、「平穏死」のガイドラインもつくりました。
ひとつだけ、伝えたいことがあります。「平穏死」という言葉は、医師が延命を行わなければ“不作為の殺人”と責任を押しつけられることを回避するという、明確な目的をもってつくったものです。決してロマンチックな意味で命名した訳ではありません。
家族も納得し、医師も安心して「看取り」をできる世の中にならなければ、患者さんを安らかにおくることはできないのです。
※週刊朝日 2012年11月30日号