
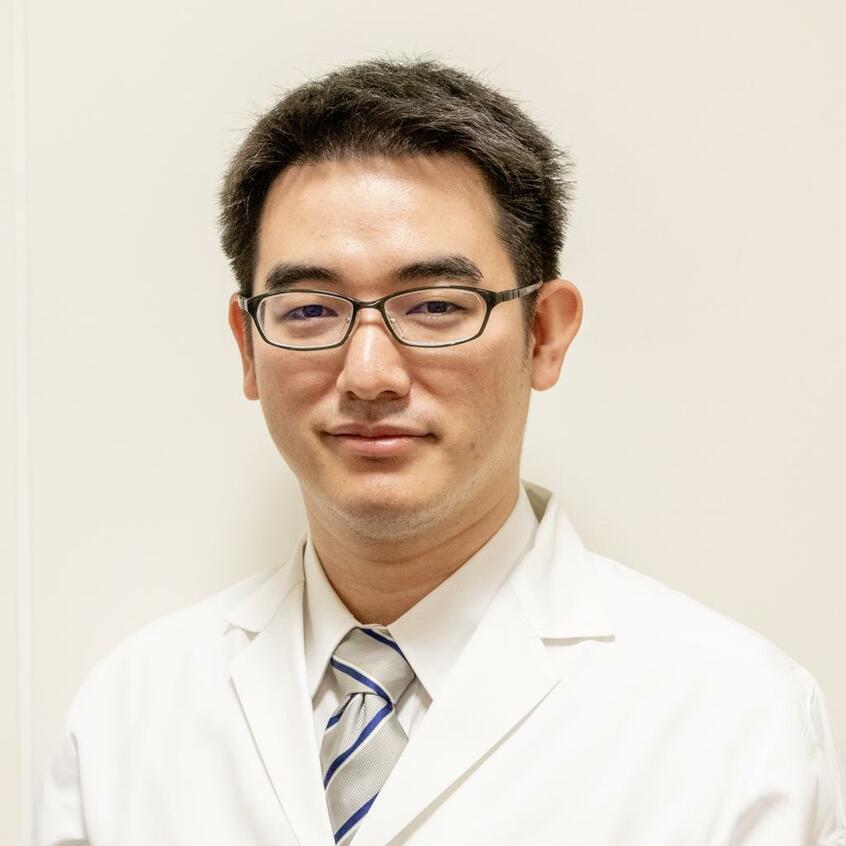
幼少期に発症することが多いと言われる吃音(きつおん)ですが、実は成人の100人に1人ということをご存じでしょうか? 言葉の最初の文字を繰り返し発声してしまう「連発」など、いくつかのパターンがあることは知られていますが、いまだに確実な治療法は見つかっていません。国立成育医療研究センター・耳鼻咽喉科の富里周太医師は大人の吃音について、「なくそうとするのではなく、吃音とともに楽しく生きよう」と提案します。その理由は、吃音だけでなく、吃音のその先にある別の疾患ともかかわっていました。
* * *
吃音の原因はいまだにわかっておらず、確実な治療法もまだ見つかっていません。そこで当事者が吃音を回避するために行う工夫のひとつが「言い換え」です。特定の文字から始まる言葉が言いにくいため、同じ意味の別の言葉に変えたり、文章の順番を入れ替えたりする工夫です。吃音をもっている人は勝手にできてしまうものです。
ただ言い換えを多用して、意味が本来の意味とかけ離れた文になってしまうということもあります。例えばキャベツを「緑で丸い野菜」と言い換えても、「レタスのこと?」などと解釈が分かれてしまいますよね。「あの野菜」「この野菜」「さっき使ったやつ」など、よりあいまいな表現になることもあります。キャベツならともかく、たとえば電話で受けた伝言が言い換えによって本来の意味どおり伝えられない、といったことになると、仕事にも支障が出てしまいます。言い換えだけでは難しい部分もあるのです。
吃音外来にいらっしゃる大人は、人によってさまざまな悩みを持っています。特定の場面、たとえば職場で電話を取ったときに、自分の名前が言えないから言えるようになりたいという人もいます。そういった場合は、言語聴覚士と呼ばれる言葉の専門家と協力し、どういうしゃべり方だとしゃべりやすいかなど、うまくしゃべるための技術を教えてもらったりします。




































