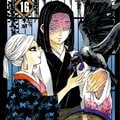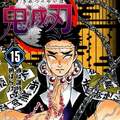人生100年、長い高齢期に備えるため一人ひとりが「資産形成」を迫られる時代。各個人は正しい金融知識を身に付ける必要があるが、学校でも会社でもお金について教わってこなかった中高年はどうすればいいのか。足りないのは何で、どう学べばいいのかを考えてみよう。
* * *
企業年金に詳しいファイナンシャルプランナー(FP)の加藤博さんは、企業型DC(確定拠出年金)の加入者に、いつもこう勧める。
「会社がやってくれる投資セミナーを利用して、ちゃんと勉強してくださいね」
企業型DCは、掛け金は会社が出してくれるが、投資信託などの金融商品を選ぶのは従業員で運用責任も従業員側が負う。従業員側の「責任」は大きいが、その代わり会社は継続的な「投資教育」を従業員に提供する努力義務がある。
「会社員がお金のことを勉強しようと思ったら、自腹で料金を払ってセミナーを受けるか、無料なんだけど後で金融商品を薦められるセミナーか、この二つがメインなんです。その点、DC制度に基づいて行われるセミナーは費用は全部、会社側が負担してくれて無料です。内容も中立的。利用しない手はないでしょう」(加藤さん)
むろん会社によって投資教育の中身は違うが、投資の経験や知識のレベル、世代別でセミナーを提供してくれるところもあるという。
「こうやって会社にいる間から少しずつお金を勉強していけばいい。しかも企業型DCをしているのだから、『長期投資』も実践して学べます。徐々に知識や経験を増やし、ほかの老後資金についても学びを生かしてほしい。退職金をどうするかも、その延長線上で考えてください」(同)
加藤さんはそれ以上は語らないが、知識がないままリタイアした会社員が、多額の退職金を抱えて金融機関に相談に行くことを恐れている。薦められるままに、良くない金融商品に手を出してしまいかねないというのだ。
加藤さんが勧める「お金の勉強」をはじめ、お金の知識・判断力を意味する「金融リテラシー」が今後、ますます注目を集めそうだ。金融庁が今後の重要方針を示す「金融行政方針」で「国民の金融リテラシーの向上」を重視する姿勢を打ち出したからだ。