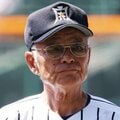文化庁が毎年発表している「国語に関する世論調査」。いつも話題になるのが言葉や慣用句の使い方だ。「役不足」「流れに棹さす」など、本来の用法とは正反対の意味で覚えている人が多い。2012年度の調査は16歳以上の男女2153人が回答した。みんなはどう答えたのか? 正解は? あなたは大丈夫?
1.「役不足」 例文:彼には役不足の仕事だ。
(ア)本人の力量に対して役目が重すぎること 51.0%
(イ)本人の力量に対して役目が軽すぎること 41.6%
→ 重要な役職に大抜擢された人が謙遜のつもりで「私には役不足で」と言ってしまうのが、よくある失敗。それでは嫌味と受け取られかねない。
2.「流れに棹さす」 例文:その発言は流れに棹さすものだ。
(ア)傾向に逆らって、ある事柄の勢いを失わせるような行為をする 59.4%
(イ)傾向に乗って、ある事柄の勢いを増すような行為をする 23.4%
→ 渡し舟の船頭さんの動作を思い出してみると・・・。
3.「気が置けない」 例文:その人は気が置けない人ですね。
(ア)相手に対して気配りや遠慮をしなくてよい 42.7%
(イ)相手に対して気配りや遠慮をしなくてはならない 47.6%
→「気がかり」「気になる」「気配り」など、「気」には心配や遠慮といった意味がこめられている。「気が置ける」はうちとけられない、という意味。
4.「潮時」 例文:そろそろ潮時だ。
(ア)ちょうどいい時期 60.0%
(イ)ものごとの終わり 36.1%
→ 潮の満ち引きが起きる時刻が「潮時」。「潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな」という歌が万葉集にある。船を出すグッドタイミングなのだ。
5.「噴飯もの」 例文:彼の発言は噴飯ものだ。
(ア)腹立たしくて仕方ないこと 49.0%
(イ)おかしくてたまらないこと 19.7%
→「憤怒」「憤懣やるかたない」の「憤」ではなく、「噴射」の「噴」。読んで字のごとく・・・。
本来の用法は、1(イ)、2(イ)、3(ア)、4(ア)、5(イ)