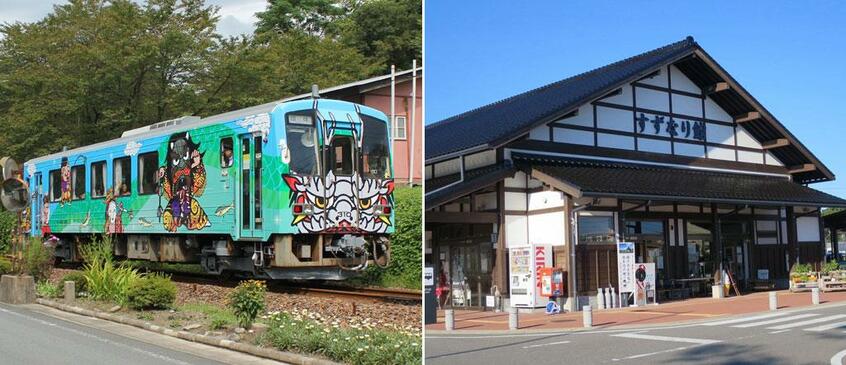
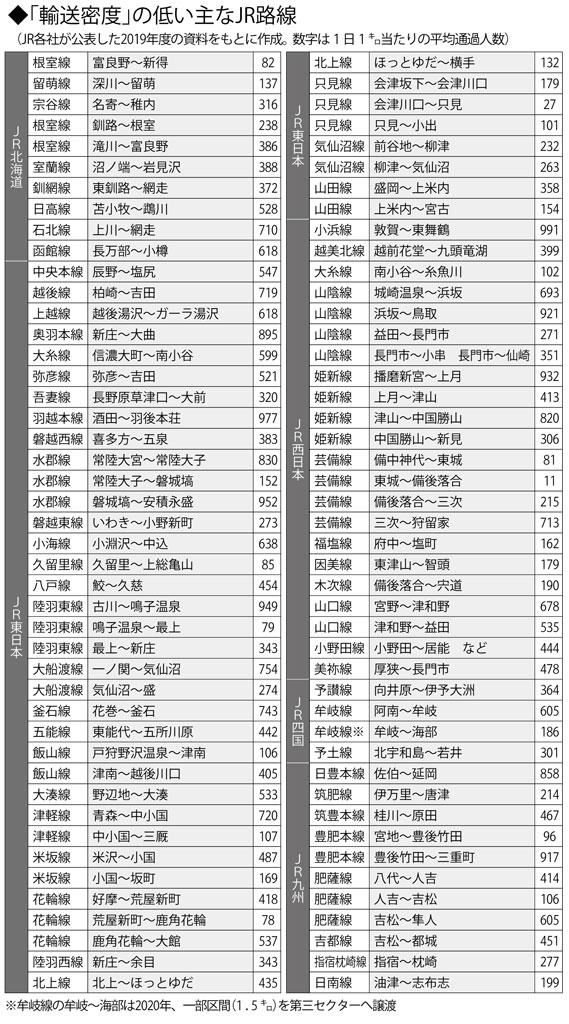
“地域の足”として生活を支えてきたローカル鉄道。少子高齢化による利用者減少で赤字路線が増えるなか、新型コロナウイルス感染拡大の影響が鉄道業界を直撃、まさに「存廃」の岐路に立つ。廃線後にバスや道の駅で再生した事例を紹介する。
* * *
赤字垂れ流しのローカル線の存廃問題は“待ったなし”だ。駅前の活気を取り戻すためにも、新たな活用に知恵と費用をかけたほうがいい。
そこで、暗い話ばかりでなく、廃線後の各地の様子や取り組みを紹介してみたい。
広島県の三次駅と島根県の江津駅を結ぶ三江線(108.1キロ)は18年、過疎化などを理由に廃止された。沿線の島根県美郷町観光協会の観光サイトは当時、川沿いに走る列車から雄大な川の景色が楽しめるなどと紹介。「そして何を隠そう、この路線は日本一の赤字路線です」と“自虐的”に宣伝した。「JR西日本で当時の輸送密度がとくに低かった」(鉄旅オブザイヤー審査委員を務める鉄道ライターの杉山淳一さん)という路線だ。
美郷町観光協会によると、橋や線路はほとんど残っている。沿線の各地ではトロッコ列車の運行や、レールバイクのイベント、トンネルを利用したチーズ製造やワインカフェに活路を見いだそうと動いている。
北海道の石勝線で、新夕張と夕張を結ぶ夕張支線(16.1キロ)は19年に廃止、127年の歴史に幕を閉じた。戦後は石炭輸送に支えられたが、炭鉱の閉山で沿線人口が減ってしまった。
現在は、廃線となった夕張支線をバスがほぼカバーし、夕張市内に入る唯一の公共交通機関となっている。鉄道の停車駅に比べると、バスの停留所の数が格段に多いことから、使いやすさはよくなっているともいえる。
北陸地方の富山港線は2006年に廃止。ここに同年、日本で初めて本格的な次世代型路面電車システム(ライトレール)が導入された。ライトレールは低床式車両で乗り降りがしやすく、人と環境にやさしい公共交通として近年、再評価されているという。




































